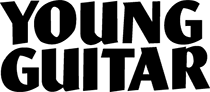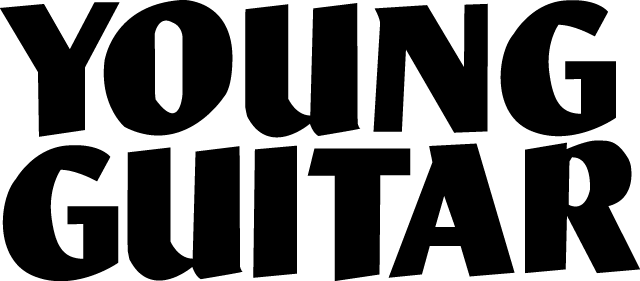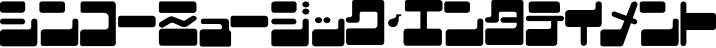2000年代後半、ACEと大橋隆志が行なっていた不定期的なジョイント・ライヴから端を発し、2011年にツアーへと発展した“RISE”。当初は「東日本大震災で疲弊した日本を元気づけるためにできることをやろう」という目的のもと、アコースティック・セッションのスタイルで始まったが、後にACEと大橋それぞれのリーダー・バンドを率いる形式になり、様々に趣向を変えながら継続する。着実に回を重ねた結果、2018年1月13日と14日に行なわれた秋葉原CLUB GOODMAN公演は、数えれば既にシーズン7。ファンの間では定番イベントとなっているこの“RISE”に、今回初めてお邪魔させていただいたが、アットホームな雰囲気の中に熱さが凝縮された実に居心地の良い時間だった。
face to ace


18:30を少し過ぎた頃、face to aceのステージが幕を開ける。時にはサポートを加えての生バンド、時には弾き語り…といった具合に、フレキシブルに様々な姿でライヴを行なう彼らだが、今回は彼らにとっての通常モード。すなわちギター&ヴォーカルを担当するACEと、シンセサイザー/ギター/その他全般を担当する本田海月という2トップの形だ。
まずLine 6“Variax”にキャパリソンのネックを搭載したお馴染みのモデリング・ギターを手に、ACEが1人登場し、ヴァン・ヘイレン的なイントロ・ソロを弾きまくると、それだけで会場の熱量が一気に上昇。やがて本田も自身のオリジナル・モデルを携えて現れ、生っぽいドラム・サウンドに乗って「SCUDERIA VINTAGE」がスタートする。ロックなリフを丁寧に奏でながらしっとりメロディーを歌うACEと、コードをかき鳴らしながら大きなアクションで観客を煽る本田という、2人の明確な役割分担は彼らの魅力の1つだ。続く「GO FOR IT!」では硬質なビートの上に心地よく歪んだオーヴァードライヴ・ギターが乗り、上下にウネウネ動くシンセ・リードと真っ直ぐな歌声が絡み合うという、分かりやすいface to aceらしさがガツンと炸裂。もちろんACEの“歌えるギター・ソロ”も言うまでもなくカッコいい。
たとえステージ上に2人しかいなくとも、彼らのライヴにはメンバーの少なさを感じさせない多彩な音がある。例えば「OLD ROBIN HOOD」ではファズ風味の混じった太いギターと尖ったシンセ・リードが派手にハモり、「LIFE」や「残像」ではアタッキーなピアノやピアニカ、エレアコのストローク、クランチーなリズム・ギターなどが渾然一体となって耳に心地よく馴染む。かと思えば表現力豊かな歌とピアノだけで成立しそうな「ノスタルジア」といった、ド直球で感動させるバラードもある。さすが長いキャリアを持つ2人だけあって、音楽性の幅の広さが半端ではない。
中間のMCにて「春先から夏にかけて新しい音源の制作に入ります!」と発表、集ったファンから待ってましたの声を浴びた後、後半はエネルギー強めのアップ・テンポ・ナンバーをノン・ストップで繰り出す彼ら。パワフルなシンセと激しいディストーション・ギターのコンビネーション・リフから始まった「SPELL ON ME」では、エース・フレーリーを思わせるトリッキーなリズムのギター・ソロでも耳を惹き、続く「TOUGH !」では飛び跳ねたくなるような裏打ちカッティング&強烈に分厚いメロディー弾きで聴かせ…。あくまでも歌がメインのポップな楽曲の中で、しっかりギター的な見せ場も作るACEは、やはりクレバーさの光るギタリストだ。また個人的には、本田が再びギターを持ってヴォーカルも務めた「FIGHT MAN」が、この夜のギター的ハイライトの1つ。スッ飛び系の音使いながらしっかりと構築されたACEのソロは、熱さと知性の両方が感じられる、実に彼らしいプレイだったように思う。
そして’70年代風味のシャッフル・リズムによる極太ギター・リフが強烈な「BE ALIVE」から、泣きのコード・プログレッションが美しいスピード感あふれるラストの「NEXT PAGE」に間髪入れず続き、一気にクライマックスへ。最高に暖まった会場を次へ引き継いで、大きな歓声を浴びながらステージを降りる2人だった。

TAKASHI O’HASHI & STEPHEN MILLS

大橋隆志は本来、待望の1stフル・アルバムを完成させたALLEY CATS LVの4人で、昨年11月に続く再来日ツアーに臨む予定だったのだが…、もう1人のギターであるブレント・マスカットの体調不良により、急遽バンドは活動休止を余儀なくされてしまった。よって今回の“RISE”を含む来日公演は、大橋とドラムのスティーヴン・ミルズに、サポート・ベーシストとして富田 毅を加えた変則的なスタイル。ではあるが、これぐらいのトラブルで百戦錬磨の彼に問題があるはずもない。イレギュラーな形を逆手にとっての、今回しか経験できない魅力的なパフォーマンスを繰り広げてくれた。
大橋の「“RISE”にようこそ!」という一言に続き、イントロのシーケンス・ビートを突き破って始まったのは、彼のソロ・ナンバー「Whole Lotta Guitars」。3ピースのバンド編成は、face to aceと全く違う意味で超シンプルだが、出て来るサウンドは激烈に重厚で密度がとてつもない。大橋はここ数年セミアコをメイン・ギターにしており、この音量ではフィードバックが物凄いことになるのではないか…と想像してしまうが、全くものともせず自由に操っているように見える。続くインスト「Rush Is Coming」も、やはり音は凄まじくヘヴィ。ジミー・ペイジばりにテルミンで猛烈なノイズを創出したかと思うと、ベース・リフに乗りながら耳に突き刺さるようなオクターヴ・ファズで乱暴にソロを奏で…、もう何もかもが強烈だ。
3曲目には先述のALLEY CATS LVの作品『WHA CHA SAY!』から、オープニングを飾る「Same Ol’ Song」が披露される。粘っこいリフとユニゾンでブルージーに歌い上げる大橋の声は、アルバムで聴けるヴォーカリストの声質とは違うが同じぐらい魅力的で、フロアから上がった歓声の大きさもそれを物語っている。続く「Brave Man Of An Era」はTHE OUTSIDERS時代の楽曲(約20年前!)だが、新しいナンバーと並んでも違和感なく聴けるのは、彼の追求して来たロックに確固とした芯が通っているからだろう。間のあるソロと分厚いコードが交互に繰り出され、ダイナミックに変わる音圧に身を委ねるのが心地よい。さらに「Rambling To The Sun Blues」では、大橋の十八番の1つと言えるギャロッピングを駆使したオープン・チューニング・リフも飛び出す。相当技巧的なのに難しさを一切感じさせず、涼しい顔で弾きこなすのが彼の巧みさだ。そして『WHA CHA SAY!』からはさらにタイトル曲も飛び出し、初めて聴いたとは思えないキャッチーなノリに、すべての観客が身体を揺らす。
さて、ここまではハードなバンド・サウンドの合間に大橋のジェントルなMCが挟まるという、比較的シリアスな雰囲気で進んで来たのだが…。ゲスト・ヴォーカルとしてThe HYPNOTIC TWINSでの盟友カワタコージが呼び込まれると、ハジけた華やかさが加わって全く別のバンドへと変貌。ジャキジャキのテレキャスターとファンキーなハーモニカをフィーチュアして始まった「Come Inside」は、アップ・テンポなリズムも相俟って実に楽しく、ハスキーでエッジが強くてそれでいて滑らかなカワタの歌声も素晴らしい。続く「Love Missile」でもその勢いは2倍増し3倍増し、ギター・リフもリズム隊もヴォーカルもすべての切れ味が鋭い。そしてラストはALLEY CATS LVのデビュー曲である「Smokin’ Johnny Thunders」。最後を熱気と勢いのあふれるギター・ソロで飾り、すべての観客の顔に満面の笑みに浮かべさせて締めくくるのだった。


SESSION
それぞれのライヴが約1時間ずつで、転換を含めると2時間半近くが既に経過していたが、この出演者がそろっていて素直に終わるはずもない。ある意味ここからが本番とも言える、両バンドのメンバー全員が一堂に介してのセッション・タイムだ。「”RISE” ROCK&ROLL!!の第三部へようこそ!」という大橋の宣言から、始まったのはザ・ビートルズで有名な「Twist And Shout」。おそらく歌えるメンバーが多いからこそのチョイスだろう、“Ah〜♪”の四声コーラスがバッチリとハマり、幕開けを陽気に飾る。それを食い足りないぐらいの短さで切り上げてから、間髪入れずつなぐのはザ・ローリング・ストーンズの「Dead Flowers」。いずれも原曲へのリスペクトが感じられる忠実なアレンジだが、だからこそプレイする6人の個性がよく分かり、何より全員肩の力が抜けて自然体なのが最高だ。楽器ファンとしてはやはり中間のソロ回しに自然と耳が惹かれ、穏やかな曲調の中でもやはりシャープな大橋、ロング・トーンとリズム遊びのバランスが面白いACE、きらびやかで派手で美しい本田のピアノ…が、彩りを添える様は観ていてテンションが上がる。

ACEと大橋に挟まれたカワタがいじり倒されるという、おそらくファンにとってはお馴染みのMCが長めに設けられているのも、こういったセッションでは大事な楽しみの1つ。大きな笑いを誘ってから始まったのは、そんな明るい空気とは対照的にメランコリックな「Cats In The Cellar」だ。大橋が作曲してACEが作詞し、大橋の『INDEPENDENT SOULS UNION』に収録された曲であり、アルバム同様にACEがリード・ヴォーカルを務める。跳ねるリズム、お洒落なコード、ストレートな歌声と哀愁ある旋律…。様々な魅力で会場から喝采を引き出した後、本編最後には大橋のソロ楽曲「Ripeness Days」の硬派なリフと“Hoo-Hoo〜♪”のコール&レスポンスで大いに盛り上がり、さらにアンコールではこれまたオリジナルへのリスペクトあふれる「20th Century Boy」(T・レックス)が飛び出す。2本のギターとシンセによる思い思いのインプロが壮絶に絡み合い、キャッチーなコーラスにいつの間にかつながるという、強烈にサイケなインタープレイも見せ、エネルギーMAXで大団円へと一気に駆け上がった。
冒頭に記したように、2011年に始まって以来コンスタントに開催され続けて来た“RISE”。ACEいわく、「普段の単独ライヴに比べれば出番は半分ぐらいの長さなのに、終わる頃にはいつも息が上がっている」そうで、この言葉が当イベントの熱さを不足なく表していると言えるだろう。今後も継続し、姿を変えて成長する様をぜひ見守りたい…、そんな風に思わされた一夜だった。