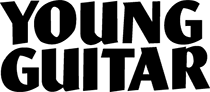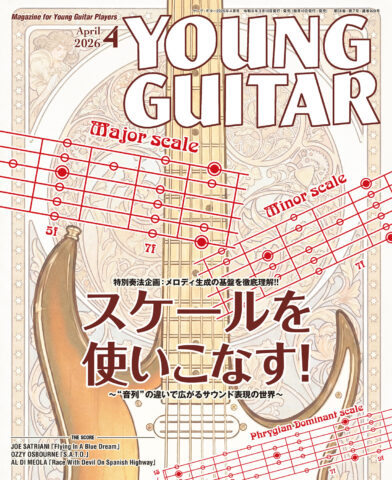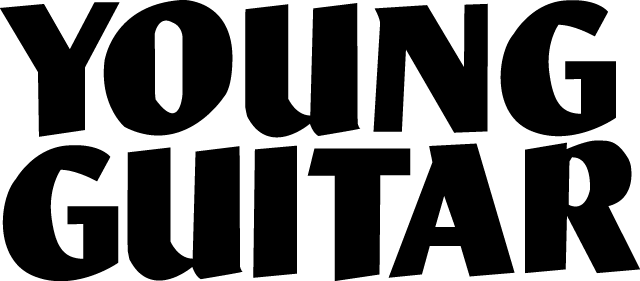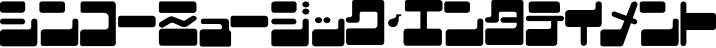1982年に結成された孤高のオルタナティヴ・ハード・ロック・バンドの筋肉少女帯が、初期曲「いくぢなし」(’85年『とろろの脳髄伝説』収録)と、大槻ケンヂ(vo)、内田雄一郎(b)、ケラ(vo/有頂天)からなる筋少の分家的テクノ・ユニット:空手バカボンの「KEEP CHEEP TRICK」「7年殺し」(共に’88年『バカボンの頭脳改革』収録)というナゴムレコード時代の3曲をカヴァーする結成40thアニヴァーサリー作品『いくぢなし(ナゴムver. サイズ)』(40周年記念ライヴのDVDも付属)を完成させた。ナゴム期再検証作とも言える今作に絡めて、別のバンドのメンバーであったが当時の筋少を知っている橘高文彦(g)と、初期メンバーとしてその渦中にいた本城聡章(g)の現筋少のツイン・ギター・チームに、ナゴムのあった“あの頃”を振り返ってもらった(本誌12月号には、収録各曲の細部を2人が語り尽くすインタビューを掲載)。
ナゴム時代のエピソード
YG:今回は結成40周年記念として、ナゴムレコード時代の筋少と空手バカボンの楽曲のカヴァーが行なわれたので、その頃の話を伺えたらと思っています。そもそも、’80年代初期に「中高生バンド合戦」というコンテスト(ヤマハ渋谷店で行なわれた“East West”の予選)があって、ナゴム時代の筋少と、橘高さんの率いるスリージー・ラスターが出演して顔見知りになったという話がありますが、この時の筋少のギタリストは本城さんだったのでしょうか?
橘高文彦:今思うと、空手バカボンだったのかもしれない。
本城聡章:少なくとも筋少はスリージー・ラスターとやってないかな。
橘高:そのコンテストの時は一緒じゃなかったかも。今でも覚えているんだけど、とにかくヤマハのスタッフの方が「すごい奴らが出てきた」と。多分大槻(ケンヂ)君のことだと思うんだけど、グチャグチャにして帰っていったと(笑)。とにかくインパクトは残していったんだな。
本城:多分その時僕は有頂天だね。有頂天はスリージーと何回か一緒になったから。で、橘高君の友達の傘を踏み潰した(笑)。
橘高:そう、俺の友達が応援にきてたんだけど、おいちゃん(本城)のパフォーマンスがやたら激しくて、客席に飛び込んでたんだよ。その日が雨で、持ってたビニール傘をおいちゃんに潰されたらしくて、「これどうしたらいいんだ」と(笑)。俺に訊くなよ!(笑) そのくらい激しかったんだよ、おいちゃんは。
本城:そうだね、当時はね(笑)。
橘高:そのコンテストに有頂天と、筋少だったか空バカだったかがいて、筋少周りのバンドもすごくいたのよ。ナゴム界隈っていろんなバンドの掛け持ちをする人がすごく多かったから。後にアルージュになるスリージー・ラスターは、’82年と’83年の“East West”の一番最初の予選会場がヤマハの渋谷店で、そこに彼らも出ていたわけだけど、俺たちは’82年に出て中野サンプラザの決勝戦まで行ったのね。それで翌年の’83年は渋谷店のシードみたいな扱いになっていて、その年に有頂天や筋少とかがいたの。BERA(石塚伯広/g)がいたバンドは何だったっけ?
本城:マイム・マイム・ダンサーズかな。
橘高:それ。それとか、筋少に関わった人たちが沢山いた。その辺の生き様がね…(スリージー・ラスターのような)ハード・ロック・バンドって純潔性が大事だったから、他のバンドを掛け持ちでやったりしてはいけない空気(笑)。ファンもアーティストも「本気じゃない」っていう感じでね。でも彼ら(ナゴム界隈)は先駆けだったのかもしれないね。その当時からコラボをいっぱいやってて、おいちゃんなんかも有頂天と筋少を掛け持ちしたりして。
本城:今「中高生バンド合戦」の動画を見つけたんだけど、これは筋少で出てた時だった。’82年の12月2日だって。
橘高:12月ということは、翌年の予選が始まっているような時期かな。決勝は確か夏だもん。
YG:その動画には本城さんがいると?
本城:いる。内田君と一緒にセーラー服を着て(笑)。
YG:爪痕を残してますね(笑)。
橘高:『ヤング・センス』だったっけ? そういう音楽系カルチャー誌があって。
本城:アマチュア・バンドとかを紹介するんだよね。
橘高:彼らがセーラー服で写ってる写真は俺も憶えてます(笑)。俺はメタラーだから『ヤング・センス』の方向性ではないんだけど、ハード・ロック・バンドも出てたんだよね。当時の若者向けカルチャー雑誌だったから。俺は音楽誌にデモ・テープを送ったりしていたからさ。
本城:スリージーはね、ちょっと違うんですよ(笑)。
YG:まさに純潔な(笑)。
本城:僕らはハナから中野サンプラザとかを目指してなかったから(笑)。
橘高:’82年ってラウドネスがデビューした翌年で、ジャパニーズ・メタル・ブームが起こっていたから。ハード・ロック・バンドがプロになれるというのが現実味を帯びてきたというか、夢を見させてもらえ始めた時代だったんだよね。アルージュは’84年にデビューしたわけだけど、コンテストに出るっていうのはプロになるためだったんだよ。SHOW-YAなんかも出ていたし。そこからメジャー・レーベルの声がかかったりして、その1つの手段としてコンテストに出ていた。でも、ナゴムの彼らがコンテストに出るのは、存在証明をしに来ていたんだよね(笑)。
本城:そうそう(笑)。もちろん、僕らのバンドがメジャー・デビューとかを考えていなかったかというと、ちょっとそこは分からないけど、スリージーたちとは違ったのは自分たちのやりたいことを手作りしていくという感覚で、あちこちのライヴハウスにどんどん出て、対バンのライヴを企画したりして。高校生なのに月に8本ぐらいのライヴを企画していたからね、こっちサイドは(笑)。
橘高:結局そっちサイドに俺は吸収合併されたんだけどね(笑)。
YG:結果的にそうなりましたね(笑)。
本城:44MAGNUMが出てきたのはラウドネスよりちょっと後だよね。僕らが昼の部でライヴを終えて、機材を片付けてたら、(夜の部に出る)44MAGNUMとマリノのメンバーの皆さんが現れて、ものすごく怖かった記憶がある(笑)。
橘高:“関西殴り込みGIG”(’82年10月24日に新宿ロフトで開催された“関西ヘヴィ・メタル東京なぐり込みギグVol.1”)の時だね(笑)。
本城:向こうにしても、なんかチャラチャラした感じの高校生がウロウロしてたら、ねえ(笑)。
橘高:そりゃ怖いよね(笑)。どっちもデビュー前夜ぐらいかな。

YG:ちなみに本城さんは、活動再開後の筋少インタビュー本『筋肉少女帯自伝』(’07年)の中で筋少とのファースト・コンタクトを回想されていて、「自分の許容範囲を超えたものが、突然目の前に現れた」と表現されていたんですが、どんなところが許容範囲外だったんでしょう?
橘高:いい表現だ(笑)。
本城:いや、あれを一目見たら誰でもそう言うと思うんだけど(笑)。多分オーケン(大槻)のことでしょ? 筋少と対バンするずっと前から、高校の先輩にケラさんがいて、一緒にやっていたから、自分としては個性の強いヴォーカルっていうのは慣れてると思っていたんですよ。でも小麦粉で顔を塗りたくって、白衣を着て、裸足でブリーフ一丁で、ひたすら奇声を発しているオーケンを見たら、許容範囲を超えているとしか言いようがない(笑)。
橘高:それが、ヤマハのスタッフが言っていた「すごい奴」のことだったんだろうね。
本城:恐らくそう。
YG:EP(当時の呼称は“ミニLP”)『とろろの脳髄伝説』のジャケに写っているようなものでしょうか?
本城:そうそう。でも、許容範囲を超えた人のバンドに僕も入るんですけどね(笑)。
橘高:俺も入ったんだけど(笑)。
YG:当時ジャパニーズ・メタルを追求していた橘高さんにとっても、当時の筋少は許容範囲外だったわけですよね?
橘高:そうだよ。今おいちゃんが言ったけど、おいちゃん(の有頂天)も俺からすると許容範囲外のグループだったんだけどね(笑)。でも彼らにしてみたら、楽器をひたすら練習しているハード・ロック・バンドっていうのも許容範囲外だったかもしれないよね。お互いが別の歩み方をしようとしていたんだけど、行き先は1つだったということになる。
本城:そうそう。
橘高:目的は一緒だったんだろうけど、まだ何も分からない当時の若者が、夢に向かっていく歩み方が違っただけであって。今だから言えることだけどね。どっちも自分たちが何者であるかを証明しようとしていたことに変わりはないわけだから。それまで多くの海外のハード・ロック・バンドを含めて、メジャーでディールを取ってツアーをして、っていうサイクルが確立されて、その動きが一番大きくなっていた時期だよね、今振り返れば。日本でもそれまでの芸能界的なシステムが、そのままロック・バンドに置き換わったような時代だったんですよ。そういう時代に、自分たちで表現して形にして、階段を登っていこうとしたのが“インディーズ”の始まりだったわけだよね。(インディーズは)メジャーに見向きもされないから自分たちでやってるんだろうと当時は思っていたけど、実はそれも1つの正解だった。なので、そのインディーズというシステムがまだ浸透していない日本において、そっちの考え方で歩んでいたグループがナゴムだったと。
一方、俺はメジャーのディールを取ることばかり考えていて、それも正解だったわけで、’84年にデビューできたんだけど、彼ら(筋少や有頂天)はその頃にナゴムレコードというものをムーヴメントにして、そこから結果的にメジャー・デビューするから、歩む先は一緒だった。時代が変わっていく間に切磋琢磨していたんだよね。逆に言うと、ナゴムは新しい時代を作ったとすら言える。X(現在のX JAPAN)やCOLORなんかもインディーズからデビューしていたよね。ヤング・ギターだって当初はメジャーから出てきたギタリストしか載っていなかったけど、今は違うでしょ? そのハシリだったと。それは脅威を感じたし、びっくりした。それが新しい時代のやり方なのかなと、横目で見ていたかな。
YG:ところで、当時のことで確認しておきたいことがあるのですが、ナゴム時代の音源を収録した『ナゴム全曲集』(’90年)のブックレットには、「いくぢなし」が入った『とろろの脳髄伝説』は’84年5月の録音という記載がありますけど、これが事実であれば本城さんの在籍期間(’82年11月~’84年7月。その後10月に一時復帰)と被ると思うんです。でも、ギターのクレジットとしてはBERAさんなんですよね。ここに収録されたオリジナル版の「いくぢなし」って、本城さんが弾いたものだったりはしないのですか?
本城:セリフのところのベース・ラインの部分を弾いたことだけはうっすらと記憶があるけど、それ以外は一切…。あれが曲としてレコーディングされたことの記憶は1mmもないんですよ。
橘高:内田君曰く、エンディングの最後に高まっていく部分はおいちゃんが作ったというんだけど、本人にその記憶は全くない。真相は闇の中。ギターを弾いたのは友森(昭一)じゃなかったっけ?
本城:BERAが弾いたのは『子どもたちのCity』(’87年にメジャー・リリースされたナゴム系オムニバス・アルバム)からだね。
──友森は’87年に加入し、EP『高木ブー伝説』(’87年)にギターとしてクレジットがある。また、『子どもたちのCity』のアルバムには’86年加入の中村“ムー”哲夫がギター担当とあるのだが、本稿では現筋少メンバー両人からの証言を尊重し、そのまま掲載している──