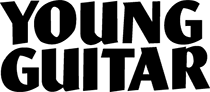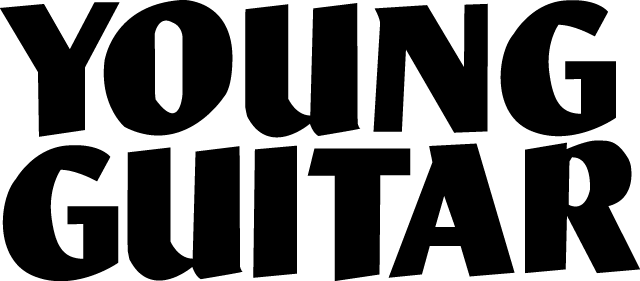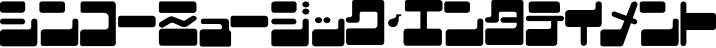長年の友人である稲葉浩志とスティーヴィー・サラスがタッグを組んだプロジェクト、INABA/SALAS。その作品もさる2月末にリリースされた『ATOMIC CHIHUAHUA』で、はや3作目を数えている。まだ作品に触れていない人は、ぜひともDVDもしくはBlu-rayが付属されている初回限定盤を手に入れることをオススメしよう。映像として収録されているのは、全国ツアー“Never Goodbye Only Hello”に向けて2人がセットリストを思案しながら行なったセッションの模様。そこでは本作の制作背景もちらほら語られているので、それを観つつアルバムを聴けば、作品に対する解像度がグッと増すはず。
さて、今回のインタビューは来日中だったスティーヴィー・サラスを迎え、そのツアー・タイトルにもなっている収録曲「ONLY HELLO part1」「ONLY HELLO part2」についての質問からスタートさせていただこう。
「誰もが永遠に生きることはできない」という問題に、どう対処するべきなのか…
YG:新作には従来のINABA/SALASらしい元気な曲もたくさんありますが、むしろアルバムの最後に収録されているメロウな「ONLY HELLO part1」「ONLY HELLO part2」が、まず非常に印象に残りました。組曲のような形になっているのも面白いですし…この曲が生まれた背景を教えてもらえますか?
スティーヴィー・サラス(以下SS):俺は自分の音楽と並行して…それこそ’80年代からなんだけど、色んなアーティストのプロデュースを手がけてきた。最近は中でも、映画やテレビ関連のプロデュースの仕事が多くなっているんだけど、その流れでスティーヴ・ヴァン・ザント(註:ブルース・スプリングスティーンのバンドで長年活躍するギタリスト)に、ブルース・スプリングスティーンの最新ドキュメンタリー映像の試写会に誘われたんだ。それを観て、色々と考えさせられることがあってね。ブルース・スプリングスティーンは若い頃の自分を「不死身」って表現していたけど…今ではもうかなり年齢を重ねている。彼はそのドキュメンタリーの中で、同世代の友人たちがどんどん亡くなっていくことに、どうやって対処していくか話していたよ。で、俺もKOSHI(稲葉浩志)と冗談っぽく言っていたあることについて思い出した。INABA/SALASの最初のツアーの時、“THE OLDEST TEENAGE IDOL IN THE WORLD(世界で最も歳を取った十代のアイドル)”と書かれたTシャツを作ったんだ。自分たちのことをからかうような意味でね。別に若返って子供になりたいわけでも、年齢より若く見られたいわけでもない。むしろ歳を重ねて、より賢くなり、人間としてより良い存在になりたいと思っている。だから俺はKOSHIに電話した。そして「君には多くのファンがいるし、若いファンにとってみれば昔からずっといる存在だ。だからこそ、こういうことについてファンに語れるような曲を作ろう」って言ったんだ。つまりこの曲は「誰もが永遠に生きることはできない」という問題に、どう対処するべきなのか…そんなテーマから生まれたわけ。
YG:結果、稲葉さんが書き上げた「ONLY HELLO part1」と「ONLY HELLO part2」の歌詞は、読んでみると非常に日本人らしい表現になっていると思いました。こういう歌詞がアメリカ人のスティーヴィーの耳に、どう響いているのかとても興味があります。
SS:俺がいろんなアーティストをプロデュースする時…例えばKOSHIと曲を作る時も、ドイツのバンドや南米のバンドと一緒に音楽を作る時も同じだけど、彼らは俺の母国語とは異なる言語で歌詞を書いている。もちろん俺にはその内容を細かく理解することはできない。それに対して俺にできるのは、メロディやフレーズに注意を払って何度も聴くこと。さらに次に、歌詞を書いた人に、どういう意図を持って書いたのかをじっくり訊ねることなんだ。KOSHIは自分が何を書いているのかを完全に理解しているし、解説してもらえれば俺もその歌詞がどんな意図を持っているのか、改めて認識できる。まあただ意味は分からなくても、KOSHIが力強く歌っているエネルギーは感じられるけどね。それに日本の女の子たちに話を聞くと、みんな「稲葉さんは女性なら誰もが聞きたいと思う言葉を歌ってくれる」って言うんだ。いつもKOSHIをそのネタでからかってるんだよ(笑)。

YG:「ONLY HELLO part1」「ONLY HELLO part2」はいずれもシンプルなアレンジで、特に前者は稲葉さんの歌声とスティーヴィーのアコースティック・ギターをメインに構成されていますよね。それぞれの曲にどんな楽器編成が最適なのか、どうやって判断しているのでしょう?
SS:俺はただ、本能に従っているだけ。例えば「ONLY HELLO part1」では、KOSHIの歌っている歌詞の邪魔になるものは何も入れるべきじゃないと考えた。思い浮かべたのは、ザ・ビートルズの「Yesterday」だ。あれはポール・マッカートニーがギターを弾きつつ、シンプルな弦楽四重奏の演奏に合わせて歌っているだけだろう? 同じような方法論が、「ONLY HELLO part1」には最も相応しいと思ったわけ。でもKISSの「Beth」のような、あまりにも壮大なストリングスは求めていなかった。あくまでもKOSHIが小さな空間で歌っているかのように、親密に感じられるようにしたかったんだ。
YG:つまり、曲に相応しいアレンジは自然と導かれて決まる…と。
SS:その通り。そして「ONLY HELLO part2」では、サンディエゴに行って、レニー・クラヴィッツのバンドで叩いているドラマーのフランクリン・ヴァンダービルトと録音した。俺が目指したのはビッグなレッド・ツェッペリンのような…例えばザ・ビートルズで言うと「Hey Jude」だ。みんなで歌って盛り上がれる、まるでデヴィッド・ボウイみたいにすごく古いサウンドにしたかった。といった具合に、それぞれの曲を聴けば何がベストなのか分かるんだよ。例えば車を買うようなもので、シートはどんなのがいいか、マニュアルがいいかオートマがいいか…色々と考えるよね?
YG:分かりやすい比喩ですね(笑)。続いて、オープニング曲「YOUNG STAR」について。この曲ではギターやリズム隊のサウンドが、まるで大きな1つの塊となって迫ってくるようで、聴いた瞬間に「まさにスティーヴィー・サラスだ!」と感じました。
SS:うん、俺のサウンドそのものだよ。実はイントロのギター・リフは、1985年に録音したものなんだ。あれは俺が高校を卒業したばかりの頃のこと。友人の家のキッチンで、フォステクス製の小さな4トラック・カセットMTRを使って録音したんだ。ギターはトム・ショルツが開発したロックマンのアンプと、BOSSのオクターヴァー・ペダルを通して演奏した。すごく奇妙な音だよね。俺はこのことを長らく忘れていたんだけど、思い出したきっかけはパンデミックだ。あの頃は自由な時間がたくさんあったから、自分の音楽ルームを整理し、昔のカセットテープやDATが入った箱を見つけたわけ。「おお、すげえクールじゃん!」って思い、今回のアルバム制作で新しい曲に取り掛かる際、KOSHIに聴かせたんだよね。「どう思う? ちょっと変過ぎるかな?」ってね。そうしたら「すごくいい!」って言ってくれた。
YG:すごい話ですね!
SS:だよね。で、そのサウンドを改めて再現しようとして、レコーディングし直したんだけど…どうしても無理でね。ジム・ダンロップが最近、ロックマンのアンプのリイシュー・ペダル(“X100”)をリリースしただろ? だからあの会社で働いている友人に電話して、それを借りたりもしたよ。他にも考えうるあらゆることを試したんだけど、やっぱり上手く再現できなかった。BOSSのオーヴァードライヴとオクターヴァーも使ってみたけど、なぜか「ブー、ブー、ブー」みたいな音しか出なかった。で、結局、1985年に録音した音を“Pro Tools”でサンプリングし、編集したんだよ。CDに入っているのはその音なわけ。あれから他にも色々試してみたけど、一度たりとも再現できたことはないんだ。本当に奇妙だよね。
YG:ちなみに稲葉さんの書いている歌詞は、ロック・スターになることを夢見ている若者について…ですよね?
SS:俺が聞いているのは、KOSHIが住んでいた町の、小さなレコード店についての話だってこと。 そのお店が“YOUNG STAR”という名前で、みんなが音楽を聴きに集まるような場所だったんだって。
YG:スティーヴィーが今話してくれた「友達の家のキッチンでレコーディングして~」という内容と、その歌詞が何となくリンクしているような気がして、面白いと思いました。
SS:それこそが、KOSHIの書く歌詞のマジックなのかもしれないね。聴く人によって、歌詞から受ける印象が違う。まさに名人技だ。