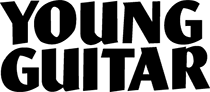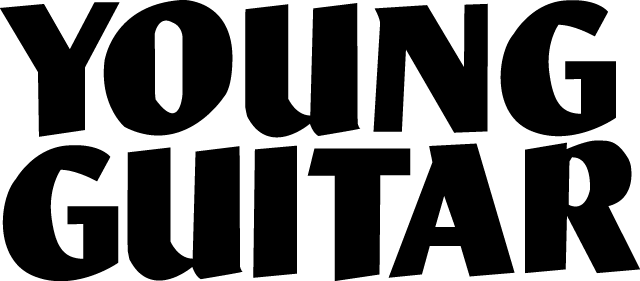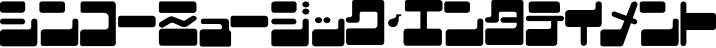ジョー・リン・ターナー(vo)も絶大な信頼を寄せる流麗なギター捌きで日本HR/HM史に名を刻んだ梶山 章。しばし表舞台からは退いていた彼が着々とシーン帰還への準備を進めているという情報は以前から耳にしていたが、その復帰作がGOLDBRICK名義のアルバムになると知った時は流石に驚いた。GOLDBRICKと言えば、梶山が森川之雄(vo)との2枚看板で結成したバンドで、’03〜’04年の間に2枚のアルバムを発表している。森川は’14年からアンセムに復帰し、以降同バンドで活躍しているだけに、まさかGOLDBRICKでも並行して活動するなんてあり得るのか?と一瞬疑問に思ったのだが、完成したアルバム『THE BOUNDARY』で歌っているのは藤井重樹という人物。NAKED MACHINEなどのバンドに在籍したことはマニアに知られているが、実質的には無名のシンガーであり、今回のGOLDBRICKでデビューを飾ることになる。
この藤井の凄まじい歌声は本作でのセールス・ポイントの1つと言えるが、それに梶山も触発されたようだ。情熱と技巧を両立した痛快な弾きっぷりを艶のある極上サウンドで披露しており、過去に発表されたどの音源よりも梶山 章というプレイヤー像がリアルに描き出されている。復帰第一弾としては十分過ぎるほどのクオリティを誇る作品が完成した。
僕が表現したいサウンドにこだわったんです
YG:梶山さんがフル・アルバムを制作するのは、下山武徳(vo/サーベル・タイガー)さんと作った『INTO THE DEEP』(’08年)以来のことになりますね。ここ数年は様々なセッションに出られたりしていましたが、それ以前に梶山さんが体調を悪くされていたということは知らなかったもので…。
梶山 章:’00年代の前半辺りから、ギターを弾く時に左手が思うように動かないなと感じていて、それがどんどん悪化していったんですよ。まあ大っぴらに病気を発表する必要もないし、そのままスルッと辞めてしまえとでも思っていました。そんなこともあって、作品をリリースするなんていうことも考えられない状況だったんですよ。
YG:GOLDBRICKとしてアルバムを作ることを決めるまでには、どのような経緯があったのでしょうか?
梶山:今回歌っている藤井重樹と出会ったのが、確か’14年頃でしたかね。病気の治療が進んで、「これならまたギターが弾けるんじゃないの?」って思ってた頃に、彼を知ったんですよ。それから藤井と一緒にセッションを色々とやっていたんです。実は最初、僕のソロ・アルバムで歌ってもらうという形で藤井をデビューさせようと考えていましてね。で、レコード会社と交渉して契約が決まって…その時点では僕のソロ・アルバム名義だったんです。ただレコード会社の方からは、ギタリストのソロというとインスト・アルバムだと思われるのではという指摘がありまして、だったらGOLDBRICKで良いんじゃないかと。森川さんさえ嫌だと言わなければGOLDBRICKにしようと、ふと思ったんです。それも今回のアルバム用のフォト・セッションが終わって着替えていた時に(笑)。すぐ森川さんに電話すると「良いじゃない」と言ってくれて、じゃあということで。最初はAkira Kajiyama Group、略してAKGなんていうのも考えましてね。でもこれだとマイクのメーカーみたいだなと(笑)。
YG:藤井さんとはSLANGRADEというバンド名でライヴをやられていた時期がありましたよね?
梶山:藤井は何でも器用に歌えるから、僕が昔ジョー・リン・ターナーと一緒に作ったアルバム(’05年『FIRE WITHOUT FLAME』)や、僕が参加したジョーのアルバム(’00年『HOLY MAN』他)の曲なんかをライヴで歌ってもらおうと思ったんです。その辺りの曲は僕としても非常に思い入れが強かったんですが、諸事情あってあまりライヴでやることができなかったんですよ。だからそういうジョーとの曲だけをやるプロジェクトを組もうということで、それに藤井がSLANGRADEという名前を付けたんです。簡単に言えば趣味の延長ですか。それもあって今回のGOLDBRICKとは基本的にまったく違うものですね。
YG:たまたまメンバーが同じというだけなんですね。
梶山:そうです。で、僕は世代的にハード・ロックと言ったらアメリカ/イギリスの音楽であるという認識があって、当時もヨーロッパの色々な国、特にドイツからもバンドが出てきていましたし、マイケル・シェンカーに影響されたギタリストも多いと思いますけど、僕はそういう影響が全然ない。やっぱりオールマン・ブラザーズ・バンドやロリー・ギャラガーみたいなアメリカ/イギリスの音楽にドップリで。その中で僕にとってはジョーがすべてにおいて最高のシンガーなんですよ。で、嬉しかったのが…。そもそも僕はジャパメタ界の速弾きキングだったわけです(笑)。
YG:「Crazy For Your Love」(プレシャスの’87年シングル/梶山のデビュー曲)のことですね(笑)。
梶山:あの曲はゲーム感覚で速弾きしていましたからね。聴いた人が「おー、弾いてる弾いてる」と笑ってくれればいいと(笑)。だから世間では「梶山は速い!」と言ってもらえていたんですが、そういう時代を経てから共演したジョーが、僕のことを速弾きを抜きにして評価してくれたというのが嬉しかったんですよ。そういうこともあってジョーとの共演は最高でした。だからさっき言ったように藤井にはジョーの曲を歌って欲しかった。今回のアルバムは僕にとっての集大成的作品にしたかったですから。
YG:藤井さんの歌声はジョーの曲にハマるし、VOW WOWのカヴァー・バンドもやっていただけあって人見元基さんのようなソウルフルな味もありますし、素晴らしいシンガーですね。
梶山:藤井は器用で、僕が求める音楽にうってつけだったんですよ。本当に何でも歌えるんで、引いちゃうことすらありました(笑)。
YG:オリジナル曲は梶山さんと藤井さんの名前がクレジットされていますが、藤井さんのヴォーカル・メロディーもお2人で一緒に作ったのでしょうか?
梶山:色々試行錯誤もあったけど、最終的には僕の作ったメロディーを歌ってもらいました。1曲目の「Cast In The Air」に関して言うと、「Crazy For Your Love」(の改作)なんですよ。思い切って僕にとっての最初の曲を頭に持ってきたんですが、最初は新しくメロを作るつもりだったんです。でもこの曲調でオリジナルと全然違うメロディーが出て来たら、聴いてる方は嫌じゃないですか。葛藤はあったけど、ギリギリ元のメロディーを残す形で作りました。
YG:以前のGOLDBRICKではキーボードは永川敏郎さん、リズム隊は陰陽座やジェラルドのメンバーがレコーディングに参加していましたよね。今回は永川さんが引続きクレジットされていますが、ドラムとベースは梶山さんの担当です。こういった形態にしたのは何故でしょうか?
梶山:今回はベースについて語らせてください(笑)。実は僕が一番こだわっているのがベースでして。大前提がピック弾きであること、プレシジョン・ベースであること(笑)。ベースには歌や上モノのケツを蹴って欲しいんですよ。「ここは行け」「ここはちょっと待て」と、そういう指揮者的な役割を持って、どっしり構えているのがベースという楽器だと思うんです。
YG:レッド・ツェッペリンで言えばジョン・ポール・ジョーンズのような?
梶山:それにウィッシュボーン・アッシュのマーティン・ターナーとかがそうですね。ベーシストを本業にしている人に頼むと、コード・チェンジの時に派手なフレーズを入れるとかしがちなんですけど、僕が欲しかったのはそういうものではない。僕の作品においてはそういうことがあっては困ると。弾いて欲しいフレーズを弾いてくれるベーシストはいるはずですが、結局僕がやった方が早いんですよ。本来のベーシストのプレイに比べたらツッコミどころが多いかもしれないけど、僕の作品だから知ったこっちゃない。ドラムに関しても同じです。
YG:ギタリストがベースを弾くと、ギター的なフレーズに走ってしまうこともあると思うんですが、梶山さんがそうならないのは全体的なプロデューサーとしての目線があるからで、だからこそ曲を引き締めるようなベースが弾けるのかもしれませんね。
梶山:そう言っていただけると嬉しいですね。ただそれは当たり前でもあるんです。やっぱり僕が聴いてきた音楽がそうだったから。ベースにしたって無駄に動くようなフレーズがなくて、全体がビシッとしているものばかり。フリーのアンディ・フレイザーだって、リードを弾いても無駄がないんですよ。
YG:ギターのレコーディングは、やはりアンプを大音量で鳴らしてマイク録りするという昔ながらの手法でしょうか?
梶山:そうですね。あまり使用機材を詳しく言うと先入観を持たれてしまうんですが、1つだけ言っておきますか。クルーズ・マニアック・サウンドの“G.O.D”は素晴らしい!(笑) これをつないでマーシャル・アンプを爆音で鳴らしてます。これは要するにトレブル・ブースターとして使っているんですよ。ストラトを弾く時にミドルを出し過ぎると、ストラトらしさがなくなっちゃうんです。やっぱりちょっと耳に突き刺さるような高音がないとストラトを使う意味がない。で、アンプ直で弾くとブーミーになりがちなんで、トレブル・ブーストでシャキッと。オーヴァードライヴとかだと濁っちゃうんですよね。ストラトの10kHzの帯域が削られるなんてあり得ない!
YG:具体的な数値が出て来る辺り、梶山さんのエンジニア魂を感じさせますね(笑)。
梶山:10kHz、5kHz、2.5kHz、この辺りは命ですから(笑)。それと使ったのはTCエレクトロニックのエコー。これは優れものでした。あの青いやつ…。
YG:“Flashback Delay”ですか?
梶山:そうですそうです。これだとテープ・エコーみたいな効果が得られるので、それとギターのヴォリューム・コントロールで音作りしています。
YG:今回のアルバム全体で聴けるギター・サウンドは、端的に“ストラトのいい音”ですよね。
梶山:嬉しいですね。今まではギターを重ねたり、ハーモニーを多用したりと、ツイン・ギター的な作り方を積極的にやっていたんですが、今回は僕が表現したいサウンドにこだわったんですよ。僕がもうすぐこの世を去ってしまうなんていう最悪の場合を考えたら、今こそ自分が後悔しないサウンドで音源を残しておくべきだと。そう考えたら理想はディープ・パープル。リッチー・ブラックモアのギター・サウンドに、ジョン・ロードのオルガンがサイド・ギター的に重なるというやつです。それをいかに実現するかっていうのが課題でしたね。ギターをダブルで録って切り貼りして…というのは、今の僕がやりたい音じゃないから。
YG:全体のミックス具合も全パートがしっかり聴き取れるバランスで、なおかつギターには迫力がありますよね。
梶山:こういうシャリシャリしたギター・サウンドって、ともすれば全体に比べるとスカスカで迫力がなくなってしまいがちなんですよね。それだけは避けたくて、あくまで現代の音として仕上げたかった。そこはエンジニアとしてもこだわったところです。マーティン・バーチ(ディープ・パープルなどを手がけたプロデューサー)を超えることを目指しました(笑)。それにヴァン・ヘイレンの1stアルバム(’78年『VAN HALEN』)だって、基本はスカスカしているけど男らしくドライヴしているじゃないですか。ああいう音楽を初めて聴いてぶっ飛んだ時の衝撃、その時の印象そのままに音作りしたんです。
YG:そういうトーンが活きていると思ったのが、「The Boundary」のバッキングでした。このバッキングの跳ねるような軽快さは、歪み過ぎていない音だからこそではないかと。
梶山:うん、ああいう感じが好きなんですよね。ストラトのヴォリュームを絞ったらもう少しモコッとするんだけど、そこはブースターのおかげでクランチ寄りのいい音になるんですね。