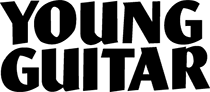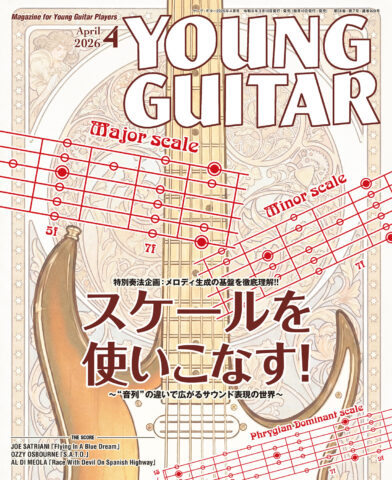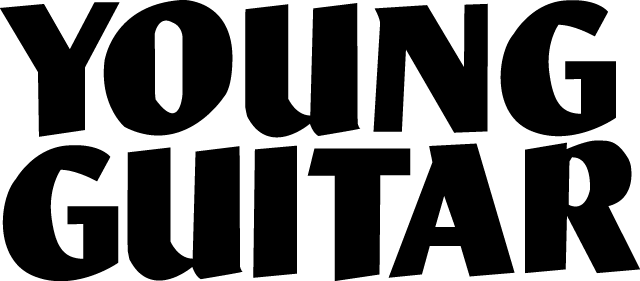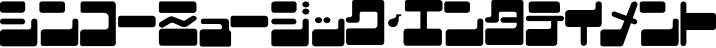約3年ぶりのソロ・アルバム『愛と調和』を、去る2020年12月23日にリリースしたSUGIZO。毎回異なる方向性で我々ギター・ファンの耳を楽しませてくれる彼だが、今作では静謐な美しさの方向に振り切り、利他的な縄文社会に影響を受けた“救済のアンビエント・ミュージック”という、予想外でもあり非常にしっくりと腑に落ちる内容でもある、そんな彼ならではの音楽を提示してくれている。未聴の方はまずYouTubeチャンネルに公開されている冒頭曲「Nova Terra(YouTube動画)」を観ていただきつつ、アルバムでは新しいミックスでまた違った表情を見せている「A Red Ray feat. miwa」(YouTube動画)にも触れてみてほしい。この2曲に魅力を感じた方は、確実にアルバムにも深くハマれるはずだ。
さて、ヤング・ギター2021年3月号の誌面には、SUGIZO自身が90分に渡ってみっちりと今作を語ってくれたインタビューの前編を掲載させていただいている。ここではより細かく各楽曲に突っ込んだ、後編をお届けしよう。両方を読み込むことで全体像がくっきりと把握できるはずだ。
一般生活では有り得ない融合が、音楽では禁じ手なしにできる

YG:2曲目「Childhood’s End」。直訳すると「子供時代の終焉」という意味ですが、このタイトルは何かを婉曲的に表しているわけでしょうか?
S:まず冒頭の「Nova Terra」で、僕の中にある理想中の理想を提示し、2曲目で一度ズドーンと現代に戻る…そういうイメージです。この現代社会の良いところも悪いところもすべて引きずって、息苦しい今の社会の状況を嘆いている、そんな感覚なんですね。痛みに苦しんでいるんです、曲の中の主人公が。今の僕らの状況は、社会的にはまだまだ幼年期であり、それを終えて次の段階に進んでいかなければいけない。そのちょうど瀬戸際に精神状態があるわけで、だから一抹の懐かしさや痛みを感じる。痛みというのは、現在を生きるからこそ感じることもあれば、次に脱皮するために感じることもあると思うんですよね。僕は陣痛だと思ってるんです、この数十年の痛みというのは。それがそろそろ終わってくれないかな…と、そういうイメージですね。
YG:何の先入観もなしにこの曲を聴くと、とてもゆったりと時間が流れるポジティヴなイメージも浮かんだんです。それは間違いではないですか?
S:もちろん、先に進みたいという思いはとてもポジティヴなので。どう感じてもらっても嬉しいですよ。この曲は作品の中でも、最も現代の人間的ですね。だからそこには慈しみ、いわゆる無償の愛というものも入っている。最終的に「Childhood’s End」という曲名になりましたけど、仮タイトルは「Salvation」、つまり「救済」だったんですよ。そういった気持ちはすごく入っています。
YG:曲中、女声のポエトリー・リーディングが入っていますよね。先ほども詩の話が出てきましたが(2021年3月号の誌面参照)、これはSUGIZOさんが書かれたのでしょうか?
S:これはある友人の詩を使わせてもらって、ペルシャ語で話していただきました。地球との共存についてを語っています。
YG:たまたま作品のテーマと合致していたものを、使わせていただいたわけですか?
S:そうですね。もっと言うと、ここにはペルシャ語もしくはアラビア語のポエトリー・リーディングを入れたいと思っていたんです。友人にそれができる人がいたので。詩の内容は後からでしたね。
YG:3曲目「A Red Ray」、これはmiwaさんのヴォーカルによる楽曲です。まずSUGIZOさん的に、miwaさんはどんな印象のあるシンガーですか?
S:ものすごく実力がある子ですね。とにかく上手い。ピッチもリズムもすごくいいし、僕が今まで一緒にやってきた女性シンガーの中でも、かなり群を抜いている実力者です。本人はあまり気付いていなかったみたいなんですけど、歌い方の節々がとてもグルーヴィなんですよね。黒人の女性シンガーが持っている、あのソウルがある。本人は「全然聴いたことないんです」って言っていたんだけど、彼女が聴いてきたミュージシャンたちが実はソウルの影響下にある白人シンガーたちだったみたいで。一般的に知られている彼女のイメージは、「元気いっぱいにみんなを応援する歌をうたう女の子」じゃないですか。それはそれで若い時にはすごく良かったんだけど、年齢を重ねて歌い手として成長していく中で、そこだけに収まらない新たな可能性が無限に広がってきたと思いますね。
YG:曲調のおかげもあるかもしれませんが、ものすごく神々しいイメージを声から受けたんですよね。思わず頭を垂れてしまうような…。miwaさんの新しい魅力を、SUGIZOさんが引き出したのかとも思います。
S:ありがとうございます。彼女にはみんなが知らない魅力がまだまだ無限にあるんですよね。本人も彼女のチームたちも、この楽曲を制作する時に「今までのキュートな女の子のイメージからどう大人のシンガーに成長していくか」ということに、とても意識を向けていたんです。その意識と合致したと言えますね。あと彼女は今、お母さんとしても頑張っているけど、ちょうどこの曲を作っている時におなかに赤ちゃんがいたんですよね。神々しさみたいなものは、もしかしたら母としてのフィーリングなのかもしれない。僕らには分からないことですけど、女性が母親になる瞬間って、人生の中でも最も重要なタイミングだと思うので。
YG:ギター的なことを言うと、1曲目、2曲目とクリーンなサウンドだけが続きましたが、この3曲目の途中でディストーションが初めて出て来ますよね。この辺りはやはり狙って考えたところですか?
S:そうですね。今回はいつものような歪みギターを極力減らし、いかにクリーンやクランチで表現できるかということを第一に考えていて。あとアコースティック・ギターですね、とても重要なのは。だからこそ、時折出てくる歪んだ音が、より強く効くだろうな…という思いはありました。
YG:クリーン・トーンからいざディストーションの音作りに立ち戻った時、奥行きのなさに苦しむことはありませんでしたか? SUGIZOさんには「釈迦に説法」かもしれませんが…(苦笑)。
S:歪み過ぎだとそうなりますよね。でも僕が欲しいサステインというのは、普通のギタリストよりも長いので、深く歪ませないと出ない。だからそれを両立させるため、ずっと僕が採り続けている方法があるんです。歪んだサウンドと、クランチを同時に出しているんですよ。そうするとバンッと弾いた時、とてもサステインが豊かでありながら、コリッとしたクランチの部分がまず耳に入る。そのやり方が、僕にとってはすごく重要ですね。
YG:4曲目「追憶」。これも1曲目と同様に音数が少ない曲ですが、にもかかわらず聴いた印象ではすごく濃密に感じられます。これは何故なんでしょう?
S:この曲は僕のギターやヴァイオリンはもちろん、ピアノやシンプルなストリング・カルテットなど、ほとんどの音がアコースティック楽器なんです。だから音数は少なくても、空気の濃密さがパックされているんだと思います。全員のエネルギーや呼吸が感じられる。シンセはもちろんアコースティックじゃないけどアナログで、いわゆるパッドの音色で空気感を作っているだけに過ぎないんですが、ただそれがとても重要で、アコースティックならではの濃密なアンビ感が録れたと思います。
YG:この曲や他の曲にも随所に入っていますが、SUGIZOさんにしか出せないヴァイオリンの、クジラの鳴き声的なサウンドがありますよね。以前から不思議に思っていたんですが、あれは一体どこから来た奏法なんでしょう?
S:どこからでしょうね、自分でも分からないんですよ。ヴァイオリンだけじゃなく、どの楽器を演奏していても、まるで生き物であるかのような表現をしたいんです。クジラやイルカというのはとても重要で、もしかしたら鳥かもしれない。鷲とか鷹とか、カモメのジョナサンかもしれない(笑)。そういう生き物の泣き声とか嘆きを音楽にしたいという思いは、昔からありますね。ギターもそうで、まさに叫んでるように弾きたい。生命力、命を感じたいのかもしれないです。
YG:5曲目「ENDLESS 〜闇を超えて〜」。この曲で歌っている大黒摩季さんに関しては、SUGIZOさんはどう捉えていますか?
S:彼女は僕と同じぐらいのキャリアを持っていて、今でも強い表現欲を持つ、好奇心とエネルギーの塊のような人ですね。アティテュードがとても近いんですよ、自分と。だからいつもすごく意気投合します。実は彼女と僕は年齢が同じで、デビューした年も同じなんですよね。
YG:同士というか、同期ですね。
S:そうそう。特にうちの真矢(dr)が20年近く大黒摩季ちゃんのファミリーというか、彼女のチームで叩いていることもあって、家族のようなイメージがあります。歌はね、もう本当のソウルがある、グルーヴ・マスターですね。いや、すごい人ですよ。
YG:音像に関して言えば、まず全体にふわっと大きな空間があり、それでいてギターはバサっと左右に分かれたりして、にじみもあるけどすごくクリアだという、相反するものを感じたんですね。この辺りのミックスも、相当苦労されたのではないかと思うんですが。
S:どの曲も苦労しましたけど、この曲に関してはまずもう、無限に広がりたかった。壮大な大陸…というか、空ですね。大きく空を舞っているようなイメージがあって。そして多分、アルバムの中でも最も激しくギターを弾いています。アンビエント的な処理はしていますけど、実は相当しっかり歪んだ音をかきむしったりしていて、そのスパークしてる感じが、広大な空のイメージと良い意味で相反する。でもとても親和性もあって、その中からさらに爆音のギター・ソロが突き抜けてくるというのが、自分の中での出しどころでしたね。この曲はいわゆるギターのヴォイシングでできてはいるんですけど、実は曲作りの初めの段階では、ほぼギターが入ってなかったんです。シンセとDAWの打ち込みだけでできていました。最後にギターをアレンジして入れた感じですね。
YG:それに尺八の音がアクセント的に聴こえたり、後半ではオルガンが分厚く入って来たり…。普通、これだけ色々な楽器を入れるとツギハギ感が出てくるんじゃないかと思うんですが、この曲にはそれが全く感じられませんね。相当練ったということでしょうか?
S:うーん…自然にそうなるんですよね(笑)。昔から自分の中で、楽器の種類に隔たりを感じないんです。おっしゃるように、パイプオルガンと尺八ってなかなか一緒にやらないですよね。そこに歪んだギターが入ってくることもあまりない。ただ僕が自身の音楽を作り始めた1997年頃から、様々な国々の楽器や音楽を融合したいという狙いは既にありました。一般生活では有り得ない融合が、音楽では禁じ手なしにできるし、そこにタブーはないじゃないですか。例えば宗教的ないざこざとか、共産主義と民主主義のいざこざとか、一般的な社会の中では相入れない要素が、音楽の中では全く無視できる。そういった手法を二十数年やってきたので、自分の中では当たり前になってしまっているんですね、おそらく。「これとこれを組み合わせたら面白いぞ」みたいな意図が、作っている時にはもうほぼないんです。ただ聴こえてくる。「ああ、ここからパイプオルガンが入ってきたら、魂を天まで引っ張ってくれそうだ」とか。ちなみに尺八に関しては、もともとこの曲はいわゆる時代劇的なアニメのタイアップから生まれたんですけど、最初の段階で和楽器をフィーチュアしたいというコンセプトがあったんです。