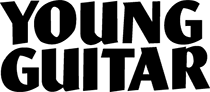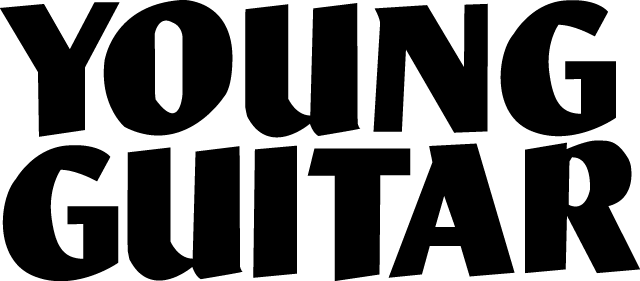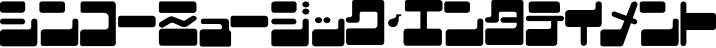レイチェル・マザー・グース(以下RMG)が 2017年にリリースした『TOKIWA NO SAI』は、彼らにとって大きな一歩であり、国産HR/HMの歴史の中でも特筆すべき1作になった。それまでRMGが発表してきた音源は、ネオ・クラシカルの申し子というイメージで捉えられていたことは否めない。しかし植木英史(g)のソロ・プロジェクト的な性格を強めたこのアルバムからは、そういった典型例から完全に脱却。韓国人シンガー:キム・ソンフンの驚異的な歌唱力を始めとした、各プレイヤーの高クオリティな演奏に支えられ、植木の思い描いていた変幻自在で壮大なプログレッシヴ・サウンドが実現したのだった。
そして2021年にリリースされた現時点での最新作『SYNRA BANSHO』は、もはや植木に何の迷いもないことを証明したさらなる力作となった。作曲/ギター・プレイの両面で持てるアイデアを出し切りつつ、あくまでキャッチーな楽曲にまとめ上げるというアレンジの妙技がさらに進化。植木の自信が音からも伝わって来る1作だ。
INFO

『SYNRA BANSHO』/Rachel Mother Goose
ルビコン・ミュージック
2021年5月26日発表
目的はこのバンドでヨーロッパに行くこと
YG:RMGは前作『TOKIWA NO SAI』からバンドと音楽の性格が大きく変化しましたが、あれから約4年以上が経ち、植木さんとしてもよりこのバンドの目指すべきものが見えるようになったという感じでしょうか?
植木英史:今となっては完全にRMGとしてのオリジナルを生み出すことに、誇りと自信を持つことができています。その証拠に、我々が『TOKIWA NO SAI』を超えたアルバムを作ったんだと、多くの人が認めてくれています。
自分にとっての座右の銘でもある“温故知新”。今までの経験と知識を駆使すれば、’60年代から現代までのロックやポップスをバランスよくアレンジして、美しいオリジナル曲ができると考えていました。そんな物語性のある唯一無二の楽曲を提供していくことが、我々の目指すところです。そしてヨーロッパに飛び込んで、どれぐらい通用するのか試したいと希望してやみません。
YG:最新作『SYNRA BANSHO』は前作譲りのプログレッシヴで多彩なアルバムですが、同時によりキャッチーなパワー・メタルらしさが増したかと感じました。前作が植木さんのやりたいことを一気に放出したアルバムだとすれば、今作はより曲にフォーカスした…というような違いはありますか?
植木:はい、各曲がとても濃厚なアレンジになっていて、リズミカルなリフが増えました。バンドとしてのコシの強さは以前からもっと欲しいと思っていましたし、もっとクールでトリッキーなリズムを打ち出すためにも、よりモダンなパワー・メタル的な音楽性が必要と考えていました。
我々は2018年と2019年に“Wacken Open Air”への出場権を争う”Metal Battle Japan”の決勝に出ることができました。よりモダンで骨太なサウンドを出すバンドたちと戦うわけですが、これは自分にとっても新しい曲を生み出すチャンスだと思い、パワー・メタル的な曲を作って出場したんです。その時に作った曲も今作に入っています。
YG:ドラムは前作リリース後からライヴに参加していた堀 博貴さんが叩いていますが、ライヴ活動を通して各メンバーの特徴をより理解したことで、前作よりもレコーディングがしやすくなったのでは?
植木:全くその通りで、前作とは違うレベルでタイトな演奏になっています。そんな演奏だからこそ音に隙間ができて、より複雑なアレンジをすることができました。20年活動をやってきて、本当に今のメンバーは最強だと、はっきり言えます。そんな素晴らしいメンバーをどう使うかは監督である自分次第です。彼らが最高の表現をするためには、自分がはっきりしたヴィジョンを持って作曲しなければなりません。
YG:「Kotodamaist」「Amatsu Kaze」というタイトルの曲があるように、今回も日本的な世界観が貫かれていますね?
植木:やはり自分たちが日本人であることを表現するのは、いずれ海外に向けて発信したいという気持ちの表れだと思います。自分の目的はこのバンドで本場のヨーロッパに行くことにあります。オリジナルな楽曲が作れる自信が付いた今、自分は日本人だという誇りも持てるようになった、そんな経緯でそのようなタイトルを思いついたのも事実です。
YG:“日本的な要素”と言うと、日本の伝統音楽を取り入れたりするミュージシャンも多いですが、RMGの場合はそういった手法を採りませんよね。
植木:いつもこう考えています。まずは何事も型にはまってみること。そこから見えてくる、型を作った先人たちの意図を知る。それを知った上でないと本当のオリジナルは作れないんですよね。まずは我々のやっている音楽の形態を作った本場ヨーロッパのサウンドを、心の底から理解するすることが基本です。それを理解した上で自国のサウンドをミックスしなければ。本当は“和”のアレンジってすごく難しいんですよね。多くの人が、好きなジャンルを安直にミックスすることを良しとしていますが、それはただ極端から極端に走っただけで、本当に自然で美しい曲というのは、深い知識と研究があってこそ成り立つものです。ですからいよいよヨーロッパに向けて表現できる場が設けられ始めたら、“和”を上手にアレンジした曲作りをしていこうと思っています。
YG:シンガーのキム・ソンフンさんは韓国の方であるわけですが、レコーディング前にはこういった日本的要素を含んだ歌詞がどういうニュアンスを持っているのか、植木さんから詳しく解説するのでしょうか?
植木:はい、各曲すべて、どのような思いで作曲したのか、その意図や歌詞の背景を伝えます。お互いに母国語が英語ではないので伝えるのは苦労しますが。やっぱり彼は言葉を吹き込むシンガーであって、そこはしっかり理解してその情景に浸りながら表現したいはずですからね。彼が自信をもってメッセージを歌うことも、やっぱりリーダーの自分がどれだけはっきり考えを持っていて、それを彼に100%伝えられるかで決まります。
YG:1曲、キムさんが作詞でクレジットされている「Why So Serious?」もありますね。
植木:自分が「Why So Serious?」の作詞に手間取っていた時、彼がこの曲をとても気に入ったから作詞したいと言ってきたんです。以前から「次のアルバムで作曲や作詞をしたい」という彼からの要望がありましてね。彼がこのバンドのシンガーなんだという責任感が高まり、ヴォーカリストとしてより100%に近い自己表現を追求したくなった表れだと思います。基本はすべて自分の責任で始めたソロ・プロジェクトですから、人に任せるのはおかしなことですが、それでもメンバーが絶対的な自分の居場所を作りたいというポジティヴな欲求を却下は出来ません。勿論、彼自身が作った歌詞やメロディーが一番しっくりくるのは自分も重々理解していますし。
YG:今回もネオ・クラシカルと表現できる要素は多々ありますが、クラシカルなメロディーをギターでそのまま弾くというベタな手法ではなく、民族音楽的なリズム・アプローチなどを取り入れているところにクラシック音楽を感じさせるのだという印象を抱きました。
植木:今作への影響源として考えられるのは、ザ・ビートルズ、サイモン&ガーファンクル、レッド・ツェッペリン、フォーカス、キャメル、PFM、U.K.、ウリ・ジョン・ロート、ANGRA、ドリーム・シアターなどだと思います。彼らはクラッシクと民族楽器を独自にミックスしたアレンジが出来るアーティストで、自然でドラマティックな浮遊感を出しているところが共通している。そんなアーティストたちに感銘を受けた部分が、今作に出ているんじゃないかと思います。以前のような“ネオクラ”という型でしか捉えられない作曲方法だと、ずっとレインボーやイングヴェイ・マルムスティーンなどのフォロワー的世界しか生み出せないバンドになってしまいますよね。
YG:荘厳なイントロ「Rachel In Wonderland」に続く実質的オープニング曲の「Under 500 Million」は、怒濤のパワーで疾走する曲ですね。メインとなるギター・メロディーの疾走感、ヨーロピアン・メタルのようなヴォーカル・パート、ギターとキーボードの見せ場となる各ソロ・パートと、今のRMGを象徴するような曲だと感じました。
植木:イントロのオーケストラは、自分の曲イメージをソンフンに伝えて彼が作曲したものです。壮大なイントロが欲しかったので。で、最初は「Under 500 Million」をアルバム序盤に入れようとは思っていなかったんです。キャッチーではあるけど個性が薄い感じがして。取っ掛かりはウリ・ジョン・ロートがスピード・メタルを作曲したら、こんな曲とリフを作るんじゃないかな、というイメージでした。全然そんな風に聴こえないと思いますが。
YG:「Why So Serious?」はキャッチーかつ壮大な曲で、ギター・ソロもまたスケール感が大きく、自由にテクニカルなプレイを連発するところが印象的でした。
植木:ありがとうございます。この曲は今作でも最後の方に作った曲で、僕が一番得意とする感じの曲です。歌メロやコード進行を作るのにはほとんど時間をかけていませんが、アレンジには気を遣いました。テンションを入れた現代的なユニゾンのテーマ・ラインはとても印象的です。T-SQUAREの「TRUTH」みたいな疾走感があって。ギターに関しても難しいスキッピングを取り入れて苦労しました。
YG:「Kotodamaist」は、ある種ジェント的な単音の刻みで始まりながら、煌びやかなキーボードの音がメインの旋律を奏でるなど、その対比が非常に壮大なテイストを生んでいます。
植木:そうですね、難解なリズムで人を惹きつける曲があってもいいと思いまして。今作一番のチャレンジ曲でした。この曲も2019年にサーカス・マキシマスと共演した時、実験的に披露したんです。プログレ・ファンに一体この曲がどう響くのかを試そうと。終演後に物販席で来場者から「“Kotodamaist”の入ったCDをください」と何人にも言われました。当然未発表曲ですから、「音源はありません」と答えると、一番印象に残った曲だと言ってもらえたんです。実験は成功…だからこの曲も今作に入れましたし、一番の目玉かもしれません。
YG:ソロも一筋縄ではいかない音使いの流麗なシュレッドで、難易度が高いのでは?
植木:ソロは変拍子になっていて、何度もアドリブを繰り返したデモ音源のテイクを、もう一度思い出して弾いたものです。苦労しました。
YG:「Amatsu Kaze」はメロディーがオペラティックで、バッキング・ギターにはクイーンの影響を感じました。一瞬、ギター・ソロにもブライアン・メイ的なテイストが出てくるようにも思うのですが?
植木:多くの方から「クイーンに影響を受けていませんか?」と言われましたが、ブライアン・メイはあまり意識したことはないんです。無意識のうちに誘導されてるのかもしれませんね。自分的にはザ・ビートルズの「Penny Lane」の影響で作った曲なんですよ。
YG:反面、サビのバッキングは重戦車ばりですね。
植木:確かに少し歪みが強くて、ヘヴィに感じますね。最初はスコーピオンズの「Pictured Life」のような軽いキレのバッキングを入れていたんですが、しかしやっぱり全体的に軽すぎた。結果的にあの重さがしっくりきたんです。因みに”Amatsu Kaze”はご存じの通り平安時代の和歌であり、百人一首でもおなじみの“天津風~”からきています。