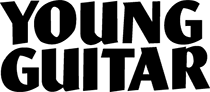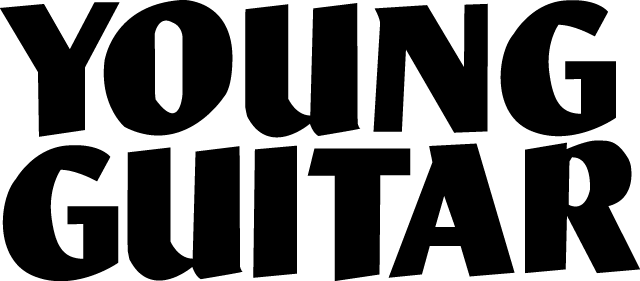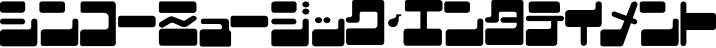北欧からは‘80年代的な快活さを持った若いメロディアス・ハード・ロック・バンドが時折登場し、その品質の高さに驚かされることがある。’09年デビューのスウェーデン産5人組:ダイナスティもその1つだった。“だった”と書くには理由がある。彼らは‘80年代ヘアー・メタルを引き合いに出されるような音楽性に囚われることなく、作を重ねるごとに硬派なメロディック・メタルの要素を取り入れていき、時にはプログレッシヴとも表現できるような個性を確立しているからだ。現在の彼らを’80年代リヴァイヴァルと表現するには言葉が足りなくなるのである。
その彼らが’17年2月中旬に初来日。東京1日だけとなったこのライヴは『TOKYO SHOWDOWN』と題されていた。来日を待ち望み続けたファンと、いかにも日本人にウケそうなマイナー調メタルを得意とするバンド、この相思相愛の両者が渋谷の地で対峙することになったわけである。その場所となった渋谷O-WESTの中は、以前に同会場で行なわれたH.E.A.T.やエクリプスの来日公演時と同様に北欧旋律派バンドのシャツを着たファンで満杯。‘16年発表の最新作『TITANIC MASS』が好評だっただけに、注目度と期待感が高まっていたことが分かる。
ライヴは疾走ナンバー「Run Amok」でスタート。せき立てるようなビートで一気に熱気が上昇し、ラヴ・マグヌソンとマイク・ラヴィアの弾く獰猛なリフが観客に襲いかかる…と思いきや、2階席で観ていた筆者の位置の問題だったのか、各パートの分離が悪くギターはかなり耳を凝らさないと聴こえない(下のフロアでは問題なかったようだが)。ただしそんな状況でも彼らの演奏力の確かさはすぐに分かる。バンド全体のパフォーマンスが思った以上に骨太濃厚、身がぎっしり詰まった感のある豪快ぶりで、マイクのシュレッド・ソロもインパクト大だ。続いては同期で鳴らされているキーボードの機械的な音から始まる「The Northern End」。往年の北欧メタル的なメロディーを持つこの曲、実にヨーロピアンである。重量感たっぷりに突き進み、マイクとラヴのツイン・ハーモニーも決まって拍手喝采。元ライオン〜バッド・ムーン・ライジングのカル・スワンを思わせる湿り気抜群なニルス・モーリンの歌唱はCDで聴いている時よりもはるかにエモーショナルで、この時点で“今日のライヴは当たりだ”という気にさせてくれる好演だ。最新作の1つ前のアルバムである『RENATUS』(’14年)から選ばれた2曲を冒頭に持って来たのは、現在の音楽性が確立したこの作品をメンバーが自信に思っているからなのだろう。

3rd『SULTANS OF SIN』(’12年)からの「Raise Your Hands」は縦ノリな曲で、サビの「Hey! Hey!」のかけ声も観客全員で大合唱だ。最新作から選ばれた「Roar Of The Underdog」はより複雑な進行の曲だが、これも当たり前のように合唱。やはりどの曲も完璧に覚えた忠実なファンが揃っているようだ。この2曲でソロを担当したのはラヴで、特に後者ではスウィープ〜タッピングの大技を繰り出しながら“顔”で弾く姿が頼もしい。ラヴだけでなくマイクにも言えることだが、速弾き技の引き出しを色々と披露しながらも、決して正確さ優先で棒立ちになるようなことはなく、感情を露にして弾くところが好印象だ。さらに2人を比較するならば(ステージ・ネームの可愛さに反して)体格がゴツいラヴの方がピックアップの切り替えなどで音色を細かく使い分けており、マイクの方がより直球に弾きまくる、というようなイメージがあった。
爽やかな快速ナンバー「Free Man’s Anthem」に続いてはスウェーデンの女性シンガー:アンナ・ベリエンダールのカヴァーである「This Is My Life」。ここではギター・チームがクリーン・トーンで切々としたバッキングを奏で、ソロ・パートではラヴが顔をしかませながら揺れ幅の大きいヴィブラートを決めていた。

ここまではどちらかと言えばシリアスでドラマティックな欧州メタルが続いたが、1st『BRING THE THUNDER』からの2曲「Light’s Out In Candyland」と「Bring The Thunder」では、一転してアメリカ色に。初期のスリージーなロック・サウンドが観客の身体を揺らす。後者でのマイクのスウィープ連発は「ノリにまかせてとことん詰め込む!」といういい意味での暴れぶりが感じられた。
ドラム・ソロを経た「The Beast Inside」で再びヘヴィ&ダークに攻めた後、「Incarnation」はラヴとマイクのフォーメーション的なアクションを見せ、途中でベースのジョナサン・オルソンによるソロも盛り込まれた。レイキングを駆使した俊速フレーズやスラップといったテクニックを披露した彼は最も新しいメンバーだが、このソロ・パート以外でも常にステージ前方で激しくプレイし、一際存在感を発揮していたことを付け加えておこう。これに続くラヴのソロはフル・ピッキングで一気にリスナーを押し込む迫力を見せた。
一旦ギター・チームが袖に消えてから始まった「Salvation」はフォーク風のメロディーを紡ぐニルスの熱唱から始まり、ステージに戻ったラヴとマイクはフォーメーション的なアクションを続けながら重いリフで観客を煽っていた。この曲のエンディングから間髪を入れず、マイクがリズム隊を率いてのギター・ソロを開始し、タッピングを多用した劇的なフレーズを展開。彼の独壇場になるのかと思いきや、ここでラヴが登場。ツイン・ハーモニーを聴かせた後は入れ替わりに彼のソロとなり、やはりタッピング技を惜しげもなく繰り出す。2人のリード・ギタリストが対等な立場でコンビを組んでいることが分かる一幕だ。
最新作のオープニングだった「The Human Paradox」ではニルスも両手を上げて観客をさらに煽りながら熱唱。この姿がまた実にカリスマティックで、いいシンガーがいるとライヴも映えるものだと痛感させられた。そして本編最後は観客とともにサビ合唱の練習をしてから「Titanic Mass」だ。ジャーマン・パワー・メタルにも通じる重心の低いリフと勇壮なメロディーが、彼らの作り出す音楽的なスケール感の大きさを証明しているかのようだ。

アンコールは簡単なメンバー紹介に続き、『RENATUS』を代表するキラー・チューンと言える「Starlight」が炸裂。マイク→ラヴのソロ・リレーもクライマックスにふさわしいパワーを発揮し、記念すべき初来日公演の最後はまさしく大団円というムードで締めくくられたのである。
総評としては、まずプレイの熱さは満点。メカニカルなフレーズを忠実に再現しながらも、ライヴならではのパーティー感も漂わせる演奏は、彼らの楽曲的な魅力を2倍にも3倍にも増幅させていたと言える。さらに大きなステージに立てば、その魅力はより一層ブーストされるのではないか、そんなイメージが容易に頭に浮かぶようなステージングだった。
- [次ページ]ラヴ・マグヌソン&マイク・ラヴィア インタビュー