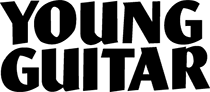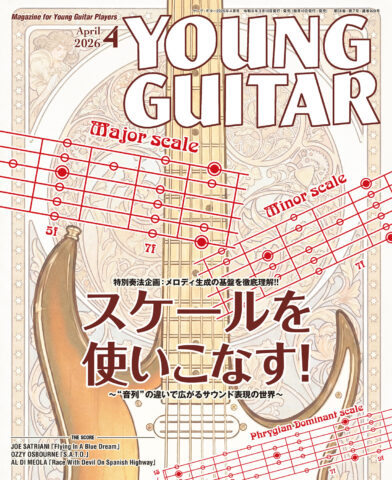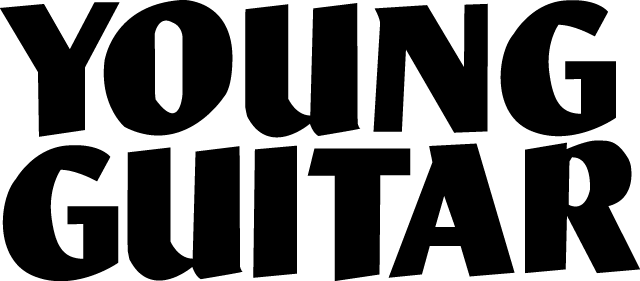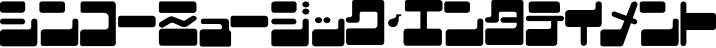B’zのギタリストとしてはもちろん、今やソロ・アーティストとしても不動の地位を確立している松本孝弘。彼がソロ名義としては通算12枚目となる新作、『Bluesman』(ブルーズマン)を2020年9月2日に発表する。これはいかにもギタリストらしいタイトルだが、実際にはギタリストとしても作曲家としても、様々な音楽の要素を彼ならではのテイストで織り交ぜているのが、作品としての肝だ。要所要所にストリングスやホーンで彩りを加えたアレンジにしても、ヴィンテージものを中心とするギターを駆使したプレイにしても、非常に陰影に富んだ味わい深いものに仕上がっている。
ヤング・ギター2020年9月号巻頭の最新インタビューでは、作品の構想、サウンド作り、楽曲とギターの選択の関係など、様々な方向から制作時の話を語ってもらっている。ここでお届けするのはその冒頭部分の抜粋だ。
このタイトルにするのが自分らしくていいと思った
YG:ソロ名義での新作『Bluesman』は、ギタリストとしてはやっぱりブルーズに立ち返るのが自然なことだ…と思わせるようなタイトルですが、ふたを開けてみるとけっこうヴァリエーション豊かな作品になっている印象ですね。
松本孝弘(以下TM):ああ、そうですか。ありがとうございます。
YG:今回収録された13曲は、どのぐらいの期間で書いたものなのでしょうか?
TM:いつも言えることなんですが、B’zのスケジュールが空いた時って、何もせずにはいられないんですよね(笑)。ただ、さあアルバムを創ろうと思い立ってから曲を書き始めた時は、ブルーズというテーマは全然決まっていなくて。まあ作業しながら出てくればいいか、という感じでした。それで最初に書いたのが、アルバムの曲順で言うと最後に収録されている「Lovely」という曲。そこからですね、どういう方向性にしようかと考えたのは。結局『Bluesman』というコンセプトが固まったのは、制作の後半になってからでした。
YG:その「Lovely」はシンプルなメロディーが印象的な曲ですが、どんな風に作っていったんでしょうか? ギターを爪弾いているうちに、自然と思い浮かぶわけですか?
TM:うですね…。どの曲にも言えることだけど、まずメロディーが先で、それにコードを付けていくっていう流れが、インストゥルメンタル曲の場合は多いかな。
YG:なるほど。『Bluesman』というテーマに関しては、どんなきっかけで決まったんでしょうか?
TM:ある程度曲が出そろった時に、「そう言えば、僕には自分の中でジャパニーズ・ブルーズマンになりたいという目標がずっとあったな」と。だから今回は『Bluesman』というタイトルにするのが、自分らしくていいと思ったんですよね。
YG:確かにどの曲も、メロディーやギター・ソロにはブルージーなテイストはたくさん入っていますが、その一方でいわゆるブルーズとは違う要素もたくさん入っている印象です。
TM:何と言うか、世間のみなさんが思われるようなブルーズっていう音楽のジャンルとは違うかもしれないけれど、例えば「月光かりの如く」とか「花火」とか、ちょっと日本的なものも自分の中ではブルーズなんですよね。
YG:音楽のスタイルとしてのブルーズというよりも、むしろ精神的な意味でのブルーズということでしょうか。
TM:そう言えるかも知れませんね。
YG:感情をストレートに表現するのが、ブルーズの神髄でもあるでしょうから。
TM:そうですね。僕がよく言っているのは、例えばロックンロールっていうのは、自分にとってカッコいいものの象徴であったりするんですよね。でもブルーズとなると、それはもう少し内面的なものなんですよ。自分の中での心の動きというか、もっとメンタル面を表しているところがありますよね。
YG:例えば「Here Comes the Taxman」のように、出だしの部分ではギターがクリーンでメロウなサウンドで、途中からものすごく派手なサウンドになる…といった展開などが、感情の激しい変化を表現しているわけでしょうか?
TM:うーん…。まあそういうのは感覚的なもので、あまり考えてないんですけどね。
YG:この曲なんかはかなりドラマティックな展開を持っていますが、作曲の段階でも最終的な流れの順に書いていった感じでしょうか?
TM:そうです。この曲はわりと始めのほうに出来た曲でしたね。おそらく3曲目ぐらいだったんじゃないかな。
YG:ではこの流れで、収録曲について細かくお聞かせください。1曲目の「BOOGIE WOOGIE AZB 10」は、とても派手でインパクトが強い曲ですが、タイトルは麻布十番へのオマージュの意味もあるのでしょうか?
TM:まあ、そうですかね(笑)。タイトルの読みは「ブギウギ エーズィービー テン」なんですけどね。麻布十番でもいいですけど。
YG:「御堂筋BLUE」(2002年『華』収録)、「Roppongi Noise」(2016年『enigma』収録)、「Omotesando」(2017年『Electric Island, Acoustic Sea』収録)に続く地名シリーズではないんですか?
TM:それ、よく言われるんですけど、別にシリーズ化しようと考えて創っているわけではないんですよ(笑)。でも何故か毎回、何かしら地名のタイトルを付けた曲がありますよね。どうしてか分からないけど。
YG:そういう曲のタイトルは、作業のどのあたりで決まるんでしょうか?
TM:付けるのはだいたい曲の全貌が見えてからですね。
YG:全貌が見えるまで、アレンジや構成はかなり紆余曲折があるんですか?
TM:曲によって、わりとすんなり決まるものもあれば、最終形に至るまでに時間のかかるものもありますね。
YG:先ほどの「Here Comes the Taxman」や、ミュージック・ビデオも撮影した「Waltz in Blue」などは、かなり凝った構成になっていますよね。
TM:そうですよね。でも構成が複雑だったりちょっと大作だったりするものばかりが、いつも大変だとは限らないんですよね。そういうものに限ってけっこうすんなり出来ちゃったりして。逆にシンプルな曲の方が、何度も変更を重ねたりすることはよくあります。そういう意味では、「Waltz in Blue」もわりとすんなりと出来ましたね。
YG:その「Waltz in Blue」は、1曲前の「漣 < sazanami >」と波の音でつながっているのが面白いですよね。この2曲は最初から、メドレーにするつもりで書いたのですか?
TM:最初はどうだったかなあ。録音作業は別々だったんですが、自分の中ではこの2曲で1セットみたいな、そういう構想はあったと思います。
YG:つまり波の音が、最初から共通するモチーフとしてあったわけですね。
TM:そうですね。僕は都会の音も好きだけれど、波のような自然の音は人の気持ちとか心の微妙な動きみたいなものを表現するには、とても良いモチーフだと思っていますね。