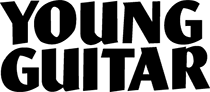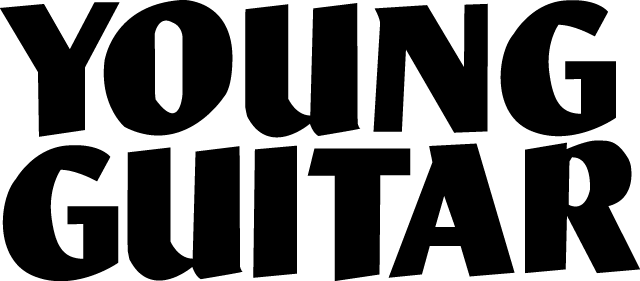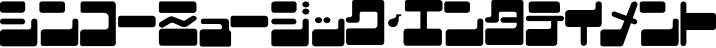昨年9月、初めての来日公演を果たしたカナダのプログレッシヴ・バンド:インターヴァルズ。多くのオーディエンスを魅了し、凄まじい反響を残したライヴの様子は先日レポートしただが、今回は18日の東京公演の翌日に行なわれた、バンドのブレーン:アーロン・マーシャルのインタビューを掲載しよう。発売中の新作『THE WAY FORWARD』(’17年)でも分かる通り、非常に緻密な楽曲を作るその音楽性から、彼には気難しそうなイメージを抱いていたが、実際に会ってみると気さくで、常に笑顔を絶やさない温かな人間性の持ち主であった。ここではアーロンのギタリストとしての姿勢はもちろん、曲を作る際に受けるインスピレーションについて等、作曲家としての側面を掘り下げた話も多く聞くことができた。
自分より先に親が上手くなるのが許せなくなってきて…
YG:まず、2日間に渡る公演お疲れ様でした。
アーロン・マーシャル(以下AM):ありがとう!
YG:18日の東京公演を拝見しましたが、凄まじい盛り上がりでしたね!
AM:そうだね。オーディエンスからとても高いエネルギーを感じて、驚きと同時に凄く嬉しかったよ。
YG:初めての日本の印象はいかがでしたか?
AM:すっかり惚れ込んでしまったよ(笑)。2週間ほど前からアジア・ツアーを行なっているけど、どこへ行っても新鮮で素晴らしい発見があるんだ。特に大阪は、来た瞬間から景色や文化に凄く感動したね。実は今回日本へ来る前に、来日経験のある知り合いのバンドから「観客は礼儀正しいけど、その分もの静かで控えめな人ばかりだよ」って言われたんだ。確かに日本人は礼儀正しく、行儀の良い聴き方をするかもしれないけど、他の国よりもずっとワイルドな反応をしてくれたね。中でも東京は特に凄いと思ったし、みんな笑顔で聴いてくれたよ。台湾に行った時も、プロモーターに「台湾人は凄く保守的だから一応警告しておくね」と言われたのに、実際は物凄くハイ・テンションなお客さんばかりだったものだから、バック転しそうなくらい驚いてしまったよ! 他にはシンガポールやタイにも行ったけど…こういった経験を通して、アジア人に対するイメージが大きく変わったよ。
YG:公演の前に行なわれたギター・クリニックも凄い反響だったそうですね。
AM:ああ。参加してくれた人達は、的を得た良い質問をたくさん投げかけてくれたよ。あとは機材についても少し尋ねられたな。通訳の人も凄くわかりやすく話してくれたしね。基本的にどこへ行っても、俺らの音楽に興味を持ってくれる人の質問は大体同じようなタイプで、ソングライティングについてだとか、インスピレーションをどこから得るのかとかそういったことが中心だ。でも、国によって質問の内容は微妙に違っていて、例えば北米やヨーロッパだと音楽業界全体に関することが若干多い。どうやってメーカーの関係者と知り合えたのかとか、どうやってレーベルと契約をとったのか、どんな風にSNSをプロモーション活用しているのか…といった具合にね。日本人でそういったことを聞いてくれたのは1人だけだったよ。
YG:アーロンへインタビューするのは初めてなので、バイオグラフィ的な部分も聞かせてください。まず生年月日と、ギターを弾き始めた年齢は?
AM:’89年の10月6日生まれで、カナダのトロント出身だ。初めてギターを触ったのは確か小学校6年生の頃だったかな。忘れてしまうくらい昔の話だ(笑)。
YG:(笑)。じゃあ、詳しいきっかけは覚えてない…?
AM:ええっと…、確か、音楽好きな親がDVDプレイヤーとライヴDVDを買ったところから始まったんだ。ビデオ・テープしかなかった頃はライヴ・コンサートの映像をそんなに持っていなかったけど、うちがDVDの時代に入った瞬間、たくさんの映像作品が集まってね。その中にあったサンタナの『SUPERNATURAL LIVE』(’00年)は、あまりにもクールで衝撃を受けたよ。直接俺のプレイに影響を与えてくれたわけじゃないけど、ギターを弾きたいって思ったのは間違いなく彼のおかげだね。ただ最初は、ドラムをやりたかったんだけど…うるさいからか、父親から「お前はギターをやるんだ」と言われてそのまま質屋に連れて行かれた(笑)。そこで、当時の自分の腕でギリギリ抱えられるサイズの、タカミネ製のアコースティック・ギターを買ってもらったんだ。「ちゃんと弾けるようになったら、今度はエレクトリック・ギターを買ってくれるかも!」と思って練習したけど、やっぱり最初は難しくてなかなか上手くいかなかった。でもある日学校から帰って来たら、父親が教則本を読みながら「Ode To Joy」(ベートーヴェン「交響曲第9番」4楽章の合唱パート)や「Greensleeves」(イングランドの伝統的な民謡)といった曲を俺のギターで練習していたんだ。その光景を見ている内に、自分より先に親が上手くなるのが許せなくなってきて、TAB譜を読めるようにして必死に練習を始めた(笑)。そうしていくうちにどんどんのめりこんで、現在に至るわけさ。
YG:インターヴァルズはあなたが結成したリーダー・プロジェクトで、’11年に初のEPとなる『THE SPACE BETWEEN』をリリースしていますが、それ以前にもバンドを組んでいたようですね。それらもやはり、モダンでプログレッシヴな音楽ジャンルだったのでしょうか?
AM:いや、高校時代はエモ系のポップ・パンクをやっていたよ。全身タトゥーだらけのドラマーが、DRAWING BLACK LINEというバンドに誘ってきたんだ。すぐに解散してしまったけど、その後は友人達と一緒RED ASTRAYというバンドを組んで、アヴェンジド・セヴンフォールドのカヴァーなんかをしていた。その時はもう、オリジナル曲も作ってたな。そういえば、ボン・ジョヴィの「You Give Love A Bad Name」をアトレイユがメタルコア風にアレンジしたヴァージョン(’04年『THE CURSE』収録)を校内でプレイして、みんなにドン引きされたのを覚えているよ(笑)。プログレッシヴなジャンルをやり始めたのは、RED ASTRAYの後に組んだSPEAK OF THE DEVILというバンドからだ。プロテスト・ザ・ヒーローやビトウィーン・ザ・ベリード・アンド・ミーを足した音楽性で、地元ではちょっと有名だったんだよ。
ライヴで弾く時はあえてアルバムと異なるアプローチをする
YG:では、インターヴァルズにとって初の日本盤リリースとなる『THE WAY FORWARD』についても質問させてください。制作する前に何かしらの構想はあったのでしょうか?
AM:いや、最初はまっさらなゼロの状態から始めて、曲のアイデアが固まって来た段階から自ずと青写真が出来上がってくるんだ。俺のアルバムは全部そうやって作っているよ。最初から決めてしまうと、楽しみやミステリーが減って発展も少なくなってしまうからね。ある程度湧いてきたアイデアに導かれるように1つ目の曲を作っていき、それを分析すると1つの芯が見えてくる。そこから発展させて、1枚の絵を作り上げて行くような流れでアルバムを制作するんだ。
YG:ミックス作業はどのように行なわれたのでしょうか?
AM:それはサイモン・グローヴという人に依頼したよ。彼はベーシストでもあり、俺の友人のプリニという素晴らしいギタリストのバンドで活躍しているんだ。最初はオーストラリアに住んでいる彼とデータをやり取りしていたんだけど、2017年の夏にプリニと共同でミュージック・キャンプを催した時、俺はアルバムの音源も持参して、立ち会いながらミックスしてもらったんだ。ただ、キャンプは数日間しかなかったから作業を途中で切り上げ、トロントに帰って他の仕事に取りかかったんだけど、終わった頃に、プリニ達がツアーでNYにいると聞いた。だから今度はそこまで車で飛んで行って、また一緒にミックスを続けたよ。
YG:この質問をしたのは、「Touch And Go」のイントロに定位が大きく動くフレーズがあって、まるで左耳から右耳へ通り抜けるようにトリッキーに聴こえたからなんです。他の曲に関してもギター・サウンドのミキシングに様々な仕掛けがありますよね。このようなパターンはアーロンがサイモンにリクエストしているのでしょうか?
AM:その通り! この曲の場合は、EQを駆使してラジオから聴こえる音楽を再現したかった。俺も少しオーディオの知識があるから、大体の曲はデモの段階でできるだけ具体的な音を作り込んで、エンジニアのヒントになるようにしているよ。でも、いつも上手く伝わるとは限らないし、サイモンと俺の場合、お互いが住んでいる場所の時差が12時間ほどある。そうすると別のヴァージョンをいくつか作ってもらいながらやり取りをしている内に、1日分無駄な時間が増えてしまうんだ。俺はサウンドに対してこだわりがたくさんあるから、ミックスに立ち会ったことで直接指示を出せてスムーズに進められたし、理想的なものに仕上がったよ。
YG:プレイ面では、メロディーには様々な展開を持たせていますが、バッキングは一定してタイトなリズムで弾いていますよね。これは意識してそうしているのでしょうか?
AM:ああ。バッキングをタイトなリズムで弾くのはインターヴァルズの美学と言っていい。今作の曲でいうと「Belvedere」とか「By Far And Away」のようなゆったりした曲でも常にこの弾き方を保ち続けている。一方、リードはいろんな緩急をつけて演奏することを意識しているよ。
YG:また、この曲はプレイスルー動画がYouTubeにアップロードされていますが、拝見するとあまりヴィブラートを使っていないように見えました。これは意識的に?
AM:本当かい? 気がつかなかったよ。ただすべての曲に言えることだけど、ライヴで弾く時はあえてアルバムと異なるアプローチをすることは結構あるね。曲がそういう風に進化していると思ってくれればいい。例えば曲作りの際に幾つかアイデアがあっても、アルバムを作る時は最終的なフレーズを決めて録音するわけだけど、アルバムが完成してしばらく間が空き、ライヴへの準備をする時にもう1度弾いてみると「こういう風に弾いたらもっと良くなるんじゃないか」っていう気付きや発見があるんだ。それを実践している。そうやって時の流れと共に手の感触が変わったことを受け入れ、自分のプレイに反映させていくことがクールだと思うんだ。
YG:なるほど。
AM:いやちょっと待てよ、今思い返してみたけど、確かにあの曲はメインのメロディーがかなりストレートな音ばかりだ。コーラスの部分は2本の弦を押さえながら、アーミングでヴィブラートをかけているけどね。ただ意図的にストレートにしたわけじゃなくて、自然とそうなったんだ。
YG:収録曲の中でも「Impulsively Responsible」はミュートのタイミングも絶妙でトリッキーなリズムが際立っていますね。なかなか思い付かないものだと思いますが、どのように構築しているんですか?
AM:リズム・パートは特に重要な要素だし、同時にギターでメインのリード・パートを作る作業の次に好きなんだ。ドラムが元々好きだったのが自分の右手に影響を与えているんだろうね。なぜそういったパターンが浮かんでくるのかは上手く説明できないな…。自然に聴こえなさそうでも、どこかにグルーヴのポケットのようなものがあって、その中に自由にメロディーをはめ込んでいる、って言えば良いのかな。どこからそういったインスピレーションが出てくるのかは正直よくわからない。長い間音楽をやっていて、ドラムにも没頭していたから自然に出て来るんだろうね。昔からリズムを刻むのが好きで、体や机をバタバタと叩いて学校の先生に「やめなさい」って追い出されたこともあったよ(笑)。
YG:複雑なリズムにメロディーを当てはめるのもかなり難しいと思いますが、どのようにして生まれたのでしょうか?
AM:実は日本のクリニックでも同じような質問をされたよ。ある日ソファーに座って、インスタグラム上でライヴ配信をやって練習風景を見せていたんだ。その中でBmのコードを弾いた時、急にこのメロディーが浮かんできた。そして「これは曲にしなきゃ!」と思い、始めたばかりのライヴをすぐに終わらせて(笑)、一気に完成させたんだよ。