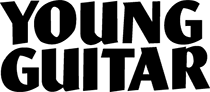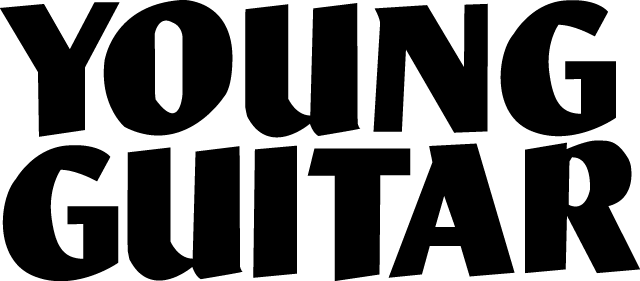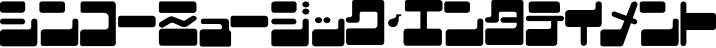2012年の再結成から断続的に活動していたT-BOLANが、遂に新しいフル・アルバムを発表。彼らが解散前に発表した1993年の『LOOZ』から数えると、6作目にして何と約28年ぶりということになる。『愛の爆弾=CHERISH ~アインシュタインからの伝言~』と名付けられたその新作は、’90年代の彼らの作品とは全く異なる質感を漂わせながらも、熱すぎる歌やシャープなギターといった核となる要素は不変。特に森友嵐士(vo)が何年にも渡る壮絶なリハビリを経て来たことを知るファンにとってみれば、感慨深いものがあるのではないだろうか(筆者もその1人だ)。そんな新作の制作秘話を、ギタリスト五味孝氏に語ってもらった。
別に久しぶりで気負うなんて気持ちもなく、ごく普通でした
YG:今回インタビューさせていただくにあたって、改めてT-BOLANの歴史を振り返ってみたのですが。1991年から1993年までの2年間でアルバムを5枚出し、そこからパタっと止まって、2022年に28年ぶりに6枚目の新作リリース…という、ものすごく面白いスパンですよね。
五味孝氏:色々ありすぎですよね。ファンの方々の中には、僕らが’90年代を通してずっと活動していたと思ってらっしゃる人も多いんですけど、実際は正味3年くらいしか活動してなかったんですよ。
YG:私も高校生の頃に聴かせてもらっていましたが、’90年代後半からパタっと音沙汰がなくなって、「どうしたんだろう?」と思っていましたし。
五味:そうですよね。後半どころじゃなくて、中盤から動いていなかったんですよ。実はね。
YG:今回、久々にアルバムを作ることになった経緯は? メジャー・デビュー30周年の節目に合わせて何かをしたい、というところから始まったわけですか?
五味:もしかすると森友と話が食い違うかもしれないですけど、僕の中にそういう意識はなかったんですよ。そもそもの始まりは“BEING LEGEND Live Tour 2012”(註:T-BOLANの他、B.B.クィーンズ、FIELD OF VIEW、DEENが参加した豪華ジョイント・ツアー)で、例えばそのタイミングで1曲作ったり、さらにその後にもシングルを何曲か出したりはしていたんですけど、アルバムまで到達できるとは正直思っていなかったんです。だけどまあ、おっしゃるとおり30周年ということもあるし、「アルバム作るぜ」っていう話になりまして。僕からすると「マジ!?」っていう感覚(笑)。
YG:“BEING LEGEND~”は私も観させていただきましたが、あそこから数えても既に10年経過しているわけですよね。
五味:1999年に解散した後、森友からはしばらくずっと音沙汰がなかったんですが、久々に再会し、リハビリ等に付き合っているうちに僕もそれに関わって…その後に“BEING LEGEND~”があったんですよね。そこで一応、T-BOLANは復活した形になったんですけど、それはあのツアー限定でした。その後、2014年にもライヴをやってみたんだけど…楽器弾きの人間とヴォーカリストの見解の違いがあったんでしょうね。森友からすると「続けるのは違う」っていうことで、結局またそこで活動休止に。でもそのタイミングで、上野博文(b)がくも膜下出血で倒れてしまって、「これは上野の(復帰するという)目標のためにも、やるしかねえか!」っていうことで、2017年に活動再開したのがそのまま今につながっているんです。
YG:今回のアルバムには、先ほどの話にもあった2012年作の「声なき声がきこえる」も入っていますが、これは本来、森友さんと近藤房之助(B.B.クィーンズ他)さんのコラボ曲だったんですよね。
五味:そうです。アレンジは増崎(孝司)さんだし、ギターも当時の音源は増崎さんが弾いてました。それを今回、僕が弾き直した感じですね。
YG:T-BOLANというバンドでの新曲という意味では、ベスト盤(2017年『T-BOLAN ~夏の終わりに BEST~ LOVE SONGS+1 & LIFE SONGS』)に入っていた「ずっと君を」、あれが最初ということですよね?
五味:そうですね。
YG:かつてのT-BOLANのイメージから外れない超王道の曲を、意図的に出してきたのかな…と思ったのですが、実際のところは?
五味:アレンジを(かつてT-BOLANの楽曲を多数手がけた)葉山たけしさんと一緒にやったので、要は’90年代からの流れですよね。だけどレコーディングのテクノロジーに関しては、完全に’90年代とは違っていたというか…家の中で完結してしまった。アンプ・シミュレーターを使ったりね。
YG:なるほど、スタジオにみんなで集まるのではなく、ファイルのデータをウェブ経由でやり取りして…ということですね。28年ぶりのアルバム制作となると、方法論からして違うと。
五味:はい。曲作りやギター入れに関しては、別に久しぶりで気負うなんて気持ちもなく、ごく普通でした。でも出来上がったものを聴いた時、森友は「涙が出た」って言ってましたね。まあ彼が歌えばT-BOLANではあるんですけど、そこに僕がギターを入れたらやっぱり違うというか、「これがT-BOLANだ!」って思えたと。僕としてはそんな気持ちで全然弾いてないんですけどね(笑)。
YG:昔のT-BOLANのアルバムでもお馴染みの、バラードの中にピンポイントで五味さんのギターが出てきて、美味しいところをかっさらうという…。
五味:ははは!
YG:そういったタイプの曲だと思いました(笑)。ソロのハーモニーはちょっとブライアン・メイ風ですが、そういう意識はなかったですか?
五味:いやいや、全然。僕は、あらかじめ考えることがないんですよ。まずギターを持って、とりあえず弾いて録っちゃう。バッキングでもソロでも。で、ファースト・テイクが良ければそれでいいというスタンスですね。ハーモニーに関しては、そのファースト・テイクの後半で「あ、ここはハモれるな」と思ったんで、少し考え直して…という感じです。
YG:なるほど、インプロからハーモニーまで自然に導かれると。
五味:そうなんですよ。よく「これ、練り込んだんですか?」って言われるんですけど、違うんですよね。もちろん少しは整理しましたけど。
YG:時間軸で話を進めると…2018年にDVDシングル「Re:I」が出ましたよね。あの曲に関してはロック路線でありながら、以前何かの折に五味さんがおっしゃっていたU2っぽい、’90年代~’00年代前半のミクスチャー・ロックの匂いがあるというか。
五味:ああ、そうですね。U2とかロクセットとかかな? そういう要素はあるかもしれないです。
YG:その路線に行き着いたのは、どういう流れだったんですか?
五味:この曲を作った時は、のちにアルバムを作るなんて毛頭思ってなかったんですけどね。例えば昔のT-BOLANだと、曲作りの時に僕がギターを弾きながら口ずさんだりした音をラジカセに録って、そういうデモをいくつも森友に渡し、彼がジャッジしていたんです。でも今は、ギターやピアノだけで「ラララー♪」って簡単に歌っただけだと、彼の耳に一切引っかからないんですよ。要はアレンジまである程度見えているものじゃないと、伝わらない。「Re:I」に関してはT-BOLANで使うことを考えず、ベーシックなアレンジを1コーラスだけ作ってあった曲だったんですね。それを森友が「これいいじゃん、やろうよ」ってことで、ブラッシュアップしていった感じです。
YG:五味さんは2010年から、恩賀周平さんとelectro 53というユニットでも活動されていますが、あそこを通ったから出てきた音なのかな…とも思いました。
五味:そうですね、完全にフィードバックされてます。
YG:そもそも五味さんが自身で、Macを使って曲全体のアレンジをこなすようになった歩みって、どういう流れだったんですか?
五味:僕はけっこう長い間、アナログ派だったんですよ。昔、カセットテープの8トラックMTRってあったじゃないですか。フォステクスとかタスカムとか。あれをずっと使っていました。でもテープだと、外部機器とのシンクがずれてしまいがちなんですよね。だから結局、最初にリズムマシンでアレンジまで想定してすべて打ち込み、それを録音した後にベースを入れてギターを入れて…っていう、今からすると面倒くさすぎる作業を。
YG:ああ~、なるほど(笑)。
五味:そんなところからスタートしましたね。で、’90年代のT-BOLANではアレンジを明石昌夫さんや葉山たけしさんと一緒にやっていたんですけど、葉山さんがMacで使っていたのが“Performer”というMIDIシーケンサー・ソフトだったんですよ。それを後ろで見ているうちに何となく操作が分かってきたので、自分でも“Performer”を使うようになって。で、レコーダーはローランドの“VS”というデジタルMTRに移行して。
YG:懐かしい!
五味:“Performer”とシンクできるようになったから、ドラムも後で直せるようになったしね。そのうちレコーディング用のソフトを“Digital Performer”に乗り換えて、そこからだいぶ自分の中で進化しましたね。どんどんデジタル化していった。
YG:それ以上の機材のお話は、改めて後でまとめてうかがうとして…。「Re:I」の前年の2017年に、森友さんが作曲して石川さゆりさんへ提供した「京恋唄」が発表されていますよね。この曲も今回、バンド・アレンジで改めて収録されています。
五味:「京恋唄」は、’90年代のようなレコーディング・スタイルでやったんですよ。ピアニストの倉田信雄さんとチェロの方で構成されているアレンジが、最初から出来上がっていたんですね。それをバンド・スタイルにするということで、まずドラムの打ち込み…これはプロデュースやアレンジやディレクションをしてくれている池田大介さんが、クリックを手打ちで入れてシンクさせて。
YG:クリックを手打ちで!
五味:要はパルスを耳で聴きながら修正しつつ、シーケンスに落とし込んでいくという。で、そこに僕がギターを入れ、森友がディレクションするという形でレコーディングを進めました。
YG:やっぱり森友さんの視点が入ってくるわけですね。1本芯を通すというか。
五味:例えば他の曲だと、僕が家で録ったアイデアを彼に送っておいて、「いいじゃない」とか「これは良くない」とか、そんな具合のやりとりなんですけどね。でもこの曲は最初から一緒にスタジオに入ってやりました。彼から具体的に「こういうフレーズ弾いて」みたいな指定はないんですけど、弾いたものに対して「違う」とか「それそれ!」とか。
YG:「違う」って漠然と言われると、すごく辛いですよね(笑)。
五味:しかも言葉が全部抽象的だからね、「雪を降らして」とか。ヴォーカリストって多いですよ、そういう人。
YG:ギターで雪を降らすのって、どうしたらいいんだろう…。
五味:なかなか降らないですよね(笑)。で、この曲はよく聴いてもらうと分かるんですけど、バッキングの音量が信じられないぐらいデカくミックスされているんですよ。
YG:確かに、歌とギターが2本柱みたいなバランスになっていますね。
五味:普段彼がジャッジすると、ヴォーカリスト的にバッキングのギターの音量は下げ気味なんですよ。だけどこの曲に関しては、ミックスの時に僕から下げてもらいました。「全然うるさくないよ」「マジで!? もうちょっとだけ下げようよ」って。
YG:普通はギタリストって、自分の音量を上げたがりますよね。
五味:そうそう。でもこの曲に関しては最初、ギターがヴォーカルよりデカかったから。まあでも森友的には、それぐらい大きくても歌の邪魔になっていないと思えるような、そういう感覚に入っちゃってたんでしょうね。
YG:それこそ私は’90年代にT-BOLANを聴いていた時、全体的にギターの音量が小さいのが悲しいな…と思っていたんですよね。だからその分、今回のアルバムはどの曲でもギターがちゃんと聴こえてくるので、いいなあと思いました(笑)。
五味:そこはね、昔森友に言われたことがあるんですよ。「お前のアレンジってさ、“ギター!”なんだよね」って。要は、いかに自分がカッコよく目立つかとか、そういう風に考えてるんだろ?みたいな。そこまで直接的には言われてないけど(笑)、だからミックスの時に小さくなりがちだったんですよね。
YG:森友さん、厳しいですね!
五味:そうですね。だからこそ、自分のフィーリングに完全にハマっていれば、どれだけ音量を上げてもうるさくない…っていう感覚なんでしょうね。
YG:でも確固たるヴィジョンを持っている人がバンドに1人いると、やっぱり全然違いますよね。
五味:まあね、時には邪魔になるけど(笑)。
YG:他の曲に関しては、アルバムを作る話が出てから書き進めたわけですか?
五味:アルバムが出るとかシングルを出すとか、そういうのに関係なく常に曲を作っていた感じですね。森友に送って音沙汰がないものとかが何十曲もある中で、「これやろうよ」とピックアップしたり、逆にあいつが作ってきた曲を「やろうよ」とか。
YG:すごく良い関係ですね、それって。
五味:ですかね?
YG:常に音楽で、商売関係なくつながっているということですもんね。ミュージシャンとして健全というか、仲の良さが見えてくるというか。
五味:なるほどね。でも音楽以外では全然関わりがないですけど(笑)。